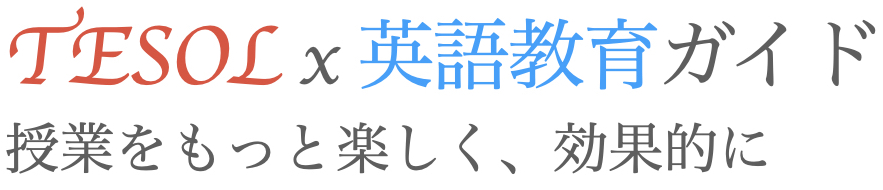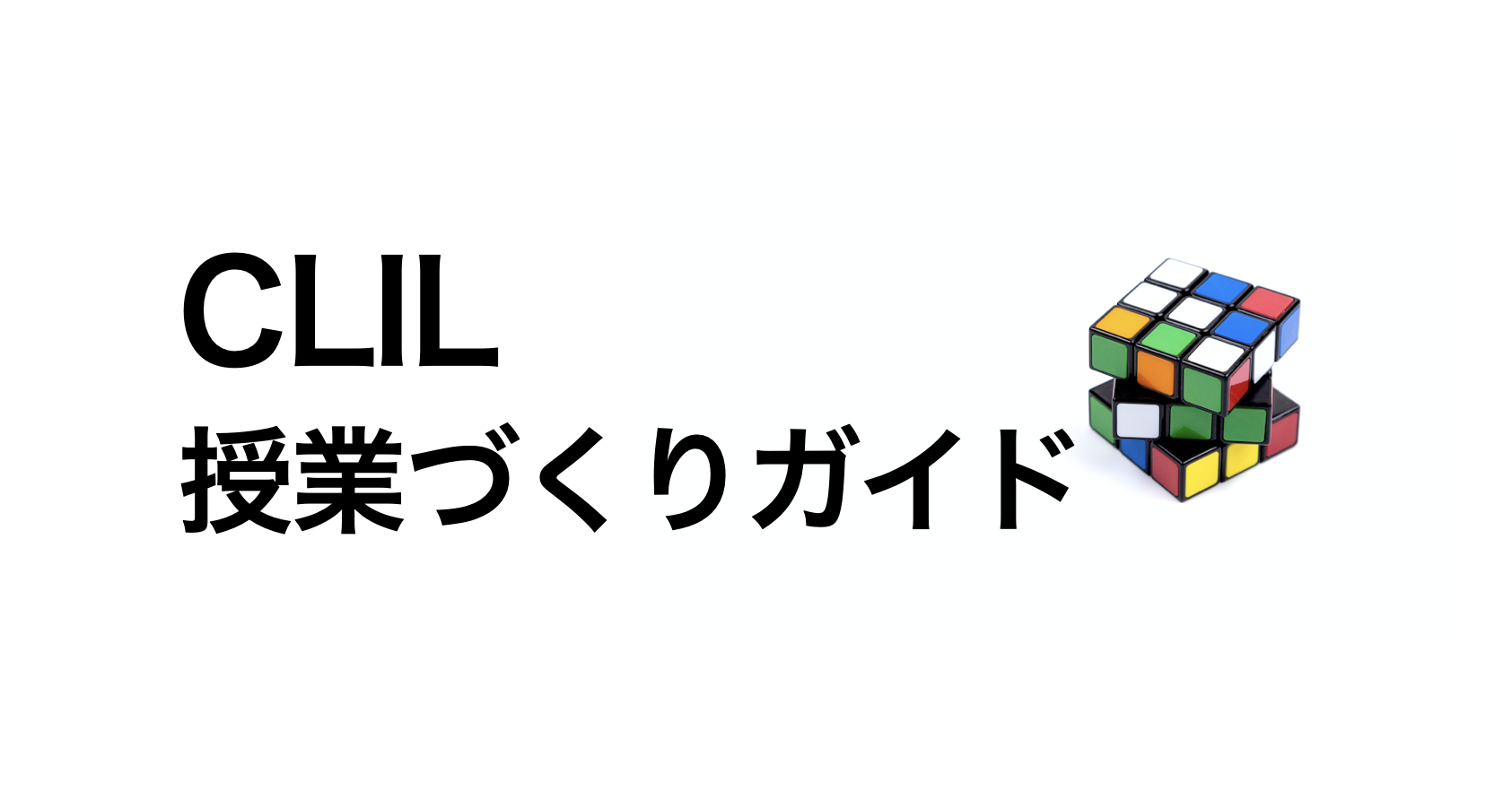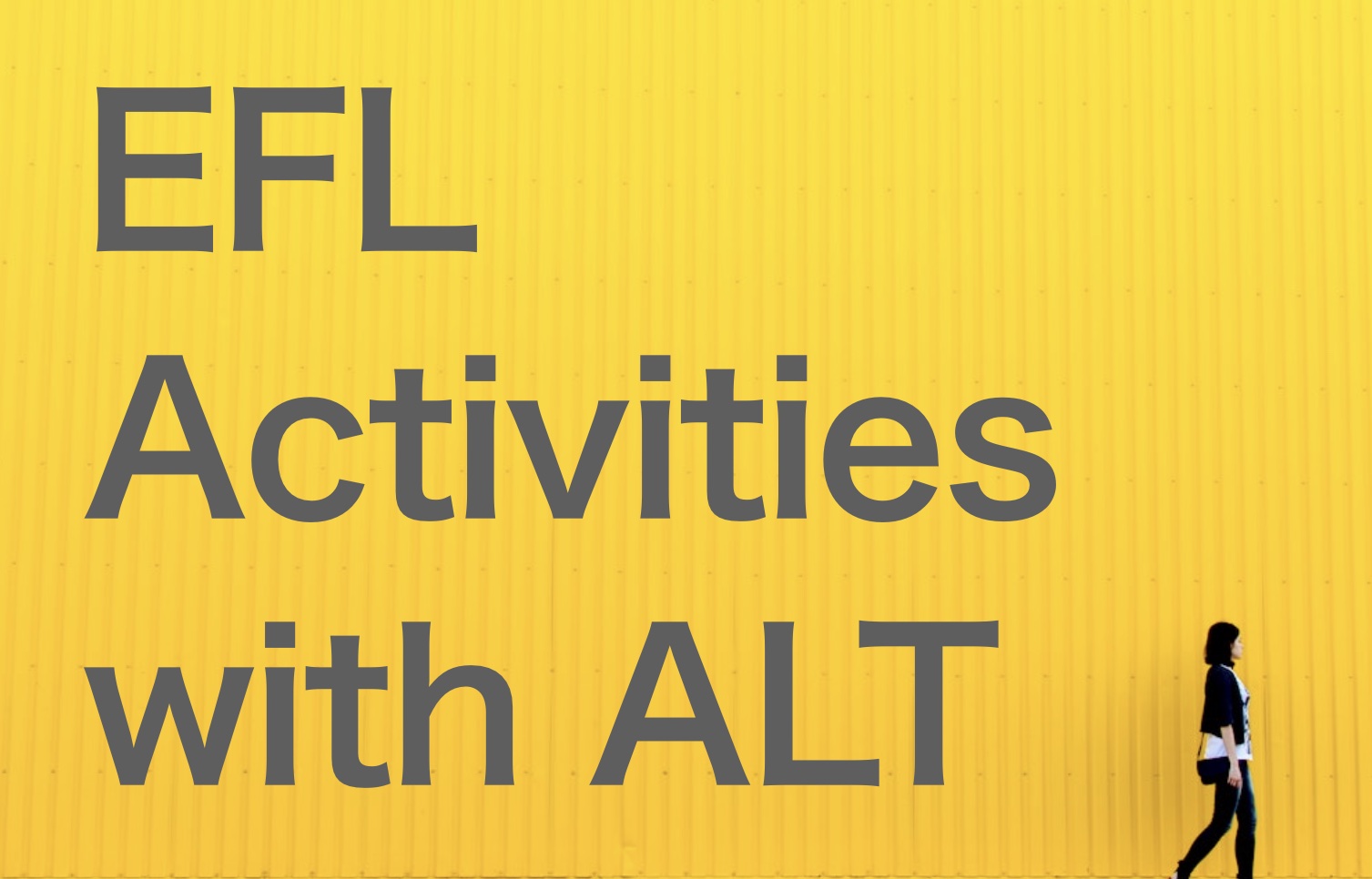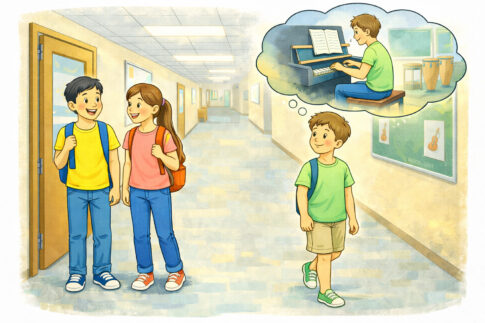英検1級、英国修士(TESOL/英語教授法)、現役英語教師のASAKOROKOです。
リスニングの指導って難しいですよね。音声を聞かせて、問題を解かせて解説して終わりになっていたりしませんか?
実は、かつての私がそうでした。ブリティッシュ・カウンシルの研修に参加した際に「それはテストであって、指導ではない。それではリスニング力はつかない」と言われた記憶があります。
では、リスニングを効果的に指導するにはどうすればいいのでしょうか。
この記事では、リスニングのプロセスから指導法、授業の進め方までしっかり解説していきます。
なお、授業づくりについては、Udemyの講座でも解説しています。Chat GPTを用いて授業準備や考査作成にかける時間を劇的に短縮する方法も解説しています。
この記事の執筆者(ASAKOROKO)
英検1級・英国修士(TESOL/英語教授法)、現役英語教師。TESOLは国際資格も保有。第二言語習得および英語指導に関する専門的な知識と経験をもとに、今回はリスニング指導の方法を解説していきます。
リスニングのプロセスを知る

リスニングはプロセスがわかれば、効果的な指導法も見えてきます。
リスニングは、以下の5つのステップから成り立っています(Tyagi, 2013)
- 受容
- 理解
- 記憶
- 判断
- 反応
受容(Receiving)
聞こえてきた音を単語として脳内で変換していく段階です。
単語自体を知らなかったり、発音を間違って覚えている生徒はこの段階でつまずきます。
理解(Understanding)
聞こえてきた単語の意味を特定する段階です。
リスニングでは、相手の話すスピードで理解していく必要があります。英文処理速度の遅い生徒はこの段階でつまずく可能性が高いです。文法の知識も必要です。
記憶(Remembering)
相手の言うことを理解するには、ひとつひとつの英単語や文を理解するだけでは不可欠です。相手が前に言ったことを記憶しておかなければなりません。
長めのリスニングに対応できない生徒は、この段階に課題があります。
判断(Evaluating)
聞き取った内容を解釈する段階です。
発話を通して相手が言わんとすることを読み取ります。この段階では、何が重要で、何がそうではないのか、見極める力が求められます。
反応(Responding)
判断をもとに、相手にリアクションを返します。リスニングというよりは、スピーキングの段階です。
Tyagi, Babita. (2013). Listening: An Important Skill and Its Various Aspects. The Criterion: An International Journal in English.
リスニングが苦手な生徒は、受容から判断までのうちいずれかに困難を抱えています。それらを適切に取り除くことで徐々に聞き取れるようになっていきます。
リスニングの効果的な指導法

リスニングの効果的な指導法は、生徒の抱える課題によって異なります。
受容段階に課題がある場合
受容段階に課題がある場合、原因は次のいずれかです。
- 語彙力が不足している
- 聞こえてくる音を単語として変換できていない
単語自体を知らない場合は、語彙力を増強させるしかありません。聞こえてくる音を単語として変換できない場合は、発音の指導が必要です。
発音を間違って覚えていたり、カタカナ英語になっている場合は発音の矯正が効果的です。音の変化も指導するとさらに効果的です。例えば、Interview は インタビュー とも発音されますが、イナビュー というように t の音が聞こえない場合もあります。
理解段階に課題がある場合
ナチュラル・スピードだと聞き取れず、ゆっくり再生すると聞き取れる場合は、英文の処理速度に問題があります。
英文の処理速度が遅い原因は、英文に触れる量が少ないことにあります。多聴・多読のような活動が効果的です。日本語でも、日常的に本を読んでいる人の方が読むのが早いですよね。英語でも、リスニングでも同じです。
比較的簡単な内容で構わないので、リスニング量を増やしていきましょう。
記憶段階に課題がある場合
記憶段階に課題があるのは、長めのリスニングで、内容を覚えていられないというケースです。
記憶段階の課題には、ノートテイキングの指導が効果的です。リーディングと同じように、最初はトピックを把握させます。次に、トピックに関連する情報をマインドマップなどを使って整理させていきましょう。
マインドマップ以外では、表に情報をまとめさせるのも効果的です。
判断に課題がある場合
判断に課題がある場合は、サマリーを書かせるようなトレーニングが効果的です。
比較的簡単なテキストを用いながら、話者が伝えようとしていることは何なのか、考えさせていきましょう。主張と根拠を書き出させたり、情報をもとに類推させるトレーニングが効果的です。
リスニング授業の進め方

ここでは、リスニング授業の進め方として、内容理解のリスニング と 語彙指導のリスニング を解説します。私自身、授業で用いています。再現性の高い方法です。
内容理解のリスニング
内容理解のリスニングは、トピックの聞き取り、情報の整理、ディクテーション、サマリーの4段階です。ディクテーションとサマリーは割愛も可能です。
リーディング同様に、全体像を把握してから細部へとアプローチするイメージで指導するとスムーズです。
*リーディングについては別の記事で解説しています。
トピックを聞き取らせる
1回目のリスニングでは、トピックを聞き取らせましょう。いきなりトピックを的確につかむのが難しい場合は、生徒が聞き取れた単語を板書させ、どのような内容について話していたのか理解させていきます。
それでも難しい場合は、写真をいくつか用意して、話している内容にもっとふさわしいものを選ばせる方法もあります。初級クラスでおすすめです。
情報を整理させる
2回目のリスニングでは、表を与え、表に書き入れる形で情報を整理させていきます。リスニング後にペアで確認させたり、必要に応じて再度再生したりしながら進めます。
ディクテーション
いきなり全てを書き取らせるのは難しいので、スクリプトの一部を穴埋めにする形式がオススメです。
穴埋めにする単語は、覚えさせたい単語か音が変化している単語がオススメです。必要に応じて発音指導も入れていきましょう。
サマリー
話の要点をまとめさせます。レベルが高い活動なので、中上級クラスで行うのがオススメです。
なお、初中級クラスで行う場合は、教師がリードし、生徒から発話を引き出す形で進める方法もあります。
語彙指導のリスニング
新出語彙の指導はリスニングでも可能です。その場合は、スキーマ(背景知識)の活性化、英単語の聞き取り、単語の確認、ディクテーションの流れがオススメです。
スキーマ(背景知識)の活性化
トピックに関する背景知識を活性化させます。関連する写真を見せて英語で説明させたり、発問を組み合わせていきます。
英単語の聞き取り
テーマに関するワードを書き取るよう指示します。例えば、天気予報を聞かせる場合は、天気に関連する単語を聞き取らせます(sunny, clear, humid, dry, high pressure, windy, etc.)
英単語の確認
聞き取れた単語をペアで確認させたり、教室全体でシェアしていきます。画像なども見せながら、生徒が意味を理解できるよう指導します。
ディクテーション
スクリプトを穴埋めする形で、テーマに関する語句を再び聞き取らせます。生徒が意味を正しく理解しているかも確認していきましょう。
授業力を高めるには? ~専門的なトレーニングが効果的
リスニング指導をはじめ、授業力を高めるには専門的なトレーニングがオススメです。授業力を高めるには経験も必要ですが、それだけでは不十分です。新しい指導技術を取り入れたり、外部からの知識をもとに自分の授業を見直す時間も必要です。
英語の授業づくりについては、Udemy でもデモレッスン付きでわかりやすく解説しています。日本の中学校や高校に対応した実践的な内容になっています。
中長期的なトレーニングならCELTA/TESOLもオススメ
中長期的に指導力を伸ばしていくには、ケンブリッジ大学認定のCELTAやTESOLの資格取得がオススメです。
英語研究の中心となっている英語圏のプログラムで学ぶことで、日本の英語教育とは違った視点から授業を考える機会にもなります。
これらはどちらも100%オンラインで、働きながら取得できます。
CELTAはスケジュールや費用の面で難しいという方には、TESOLの資格がオススメです。TESOLは、自分のペースで学習できますし、費用も大きく抑えることができ、CELTAと同じ英国資格枠組みレベル5認証のコースも取得可能です。詳しくは別の記事で解説しています。