英語の勉強を続けているのに、いざ話すとなるとことばが出てこないという経験はありませんか?「自分には向いていないのかも」と感じてしまう瞬間、誰にでもあります。
でも安心してください。英語スピーキングが伸びない原因は、あなたの努力不足ではありません。多くの場合、学び方の焦点が「理解する」ことに偏っていて、「使う」練習が不足しているだけなのです。どれだけ知識があっても、口に出して使うトレーニングを重ねなければ、話す力は“自動化”されません。そして、この“話す回路”は、正しい方法で誰でも鍛えることができます。
この記事では、英語スピーキングが伸びない5つの原因と、今日から実践できる改善法を5つ紹介します。「正確に話す」ではなく「伝える力を育てる」ことに焦点をあて、理解から発話へとつながる学習サイクルの作り方を具体的に解説します。停滞期は「伸びる前のサイン」。ここから、あなたのスピーキング力を確実に変えていきましょう。
なぜ英語スピーキングが伸びないのか

英語を勉強しているのに、いざ話すとなると言葉が出てこない。なかなか思うように話せるようにならない。多くの学習者がぶつかるこの「スピーキングが伸びない壁」には、いくつか明確な原因があります。文法や単語を理解していても、使う練習が不足していたり、思考のプロセスが日本語に依存していたりすると、実際の会話で英語が出てきません。ここでは、特に多くの学習者が見落としがちな5つの要因を整理して解説します。
原因① インプットばかりでアウトプットが少ない
理解しても使わなければ話せるようにならない
英語スピーキングの伸び悩みで最も多いのが、「理解しているのに使えない」という状態です。これは、学習が“受け身”のまま止まっていることが原因です。単語帳やリスニング教材で知識を増やしても、頭の中で整理された英語は、実際に声に出すことで初めて使える言語に変わります。インプットだけで満足しているうちは、話すための神経経路(スピーキングの回路)が作られません。
もう一つの問題は、「話す練習」の量が圧倒的に足りないことです。例えば、週に一度の英会話レッスンだけでは、話す総時間はせいぜい30〜40分程度です。筋トレを週に1回10分だけ行うようなもので、結果が出るまでに時間がかかります。“理解したことを口に出して使う”というサイクルを、日常の中でどれだけ繰り返せるかが上達の分かれ目です。
知識が増えても“使う回数”が少なければ定着しない
新しい文法やフレーズを覚えても、それを実際に会話で使う機会がなければ、脳は「重要な情報」として保持してくれません。人間の記憶は、“使用頻度”によって定着度が決まります。一度覚えた表現も、数日間使わなければあっという間に忘れてしまう。これが「覚えたはずなのに出てこない」という現象の正体です。
スピーキング力を伸ばすには、“知っている英語”を“すぐに使える英語”に変える必要があります。そのためには、学習した表現をすぐにアウトプットする「即使用の習慣」が不可欠です。たとえば、学んだフレーズをその日のうちに独り言で使ってみる、AIスピーキングアプリで言い換え練習をする、などの工夫を取り入れましょう。使う頻度が上がるほど、英語が自然と口から出るようになります。
頭の中で日本語→英語に変換している
もう一つの大きな壁は、「英語を話すときに日本語で考えてしまう」ことです。多くの学習者は、質問を聞いた瞬間に一度日本語に直し、それを頭の中で英訳しようとします。このプロセスには時間がかかるため、返答が遅れ、会話がぎこちなくなります。また、変換の過程で文法や単語の選択に意識が向きすぎ、自然な発話が難しくなってしまいます。
この「翻訳思考」は、長年の日本語中心の学習スタイルによって無意識に身についているものです。克服するには、英語を「訳すもの」ではなく「直接理解するもの」として扱う練習が必要です。英語を英語のまま理解し、反応することができるようになると、会話のテンポが格段に上がります。
「そんなの無理」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。あなたが見ず知らずの人からいきなり “I love you” と言われた場面を想像してください。いちいち、日本語に訳して、「え、この人は何言っているの?気持ち悪い」とはならないはずです。訳することなく即座に恐怖を覚えるでしょう。これこそが目指す自動化です。他の表現もそうなるくらい、徹底的に使い倒せばいいのです。
思考スピードを上げる練習が不足している
スピーキング力を伸ばすには、英語で考えるスピードを上げるトレーニングが欠かせません。リスニングで内容を理解できても、頭の中で文章を組み立てるのに時間がかかってしまうと、発話が追いつかないのです。英語で考える筋力(処理スピード)は、短い質問に素早く答える練習を通して鍛えることができます。
例えば “What did you do yesterday?” “Do you like traveling?” といった簡単な質問に、3秒以内で答える練習を繰り返すだけでも効果があります。
このトレーニングを続けると、少しずつ日本語を介さずに英語で発想できるようになります。最初は文法が崩れても構いません。大切なのは「即反応する」習慣を作ること。それが、英語脳を育て、スピーキングのスピードと自然さを引き上げる第一歩になります。
英語が話せるようになるメカニズム、トレーニング方法に興味がある方には、こちらの記事もオススメです。スピーキングを伸ばす勉強法を第二言語習得理論に基づいて科学的に解説しています。
原因② 間違いを恐れて話す機会を避けている
「正しく話そう」と意識しすぎて言葉が出ない
英語を勉強している人の中には、「間違えたくない」「恥をかきたくない」という思いが強く、話す場面になると無意識にブレーキがかかってしまう人が少なくありません。特に日本の英語教育では、諸外国と比較して正確さが重視される傾向が強く、「間違えた=ダメ」という刷り込みが深く残っています。しかし、スピーキングは“使いながら育てるスキル”であり、失敗の中で上達するプロセスが欠かせません。
この「間違いを恐れる心理」は、練習の機会そのものを奪ってしまいます。文法や発音のミスを気にしすぎて黙ってしまうと、結果的に「話さない=上達しない」という悪循環に陥ります。英語を“完璧に話す”ことを目指すよりも、「とにかく伝える」ことに意識を向けるほうが、実はスピーキング力の伸びは早いのです。
完璧主義を捨てて“伝えること”を優先しよう
英語を話すとき、最も大切なのは「伝わること」です。多少の文法ミスがあっても、相手が理解できればそれは立派なコミュニケーションです。むしろ、実際の会話では、ジェスチャー・表情・声のトーンなど、言葉以外の要素も大きな役割を果たします。つまり、“完璧な英語”よりも“伝えようとする姿勢”のほうが、相手には好印象なのです。
スピーキング練習では、「正しさ」よりも「反応の速さ」と「伝達の意識」を優先してみましょう。たとえば、“I think so.” “Maybe.” “That’s a good point.” のような、会話を途切れさせない“つなぎフレーズ”を覚えるだけでも、会話がスムーズになります。間違いを恐れず、「今ある英語でなんとか伝える」経験を積むことが、最短の上達ルートです。
それでも間違いを気にしてしまって話せない、恥ずかしいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。きっと気持ちが楽になるはずです。
原因③ 練習内容が“本番とズレている”
本番で話す内容と学習内容が一致していない
英語スピーキングが伸び悩む大きな理由の一つに、「練習の内容が実際に求められる場面と噛み合っていない」という問題があります。暗記した英文や教科書のフレーズをそのまま再現する練習では、想定外の質問に対応できません。練習で扱うタスクの種類が、本番と一致していないことこそが、停滞の最大要因と言えるでしょう。
このギャップを埋めるには、練習内容を「本番仕様」に変えることが必要です。たとえば、英検受験者なら過去の面接質問を使って意見を述べる、ビジネス英語学習者ならミーティングやメールの要約を声に出して説明してみる。“テストや会話で使う場面を想定した練習”を取り入れることで、単なる知識ではなく、その場で使える英語運用力が育っていきます。
会話を維持するための表現が不足している
もう一つの落とし穴は、「話し始めても続かない」状態です。“Yes.” “I think so.” など一言で終わってしまい、会話のキャッチボールが続かない。これは、英語の“つなぎ表現(discourse markers)”が不足していることが主な原因です。会話を維持するには、以下のような相手との流れを保つための小さな表現が欠かせません。
繋ぎ表現には、次のようなものがあります。同じような意味でも複数知っておくと言い回しがこなれてきます。
1️⃣ 例を出すとき(for example系)
- for example(たとえば)
- for instance(一例を挙げると)
- such as(〜のように)
- like(〜とか)
- to illustrate(例を使って言うと)
2️⃣ 話をつなぐ・補足する(つなぎ・追加)
- and also(さらに)
- besides(そのうえ)
- what’s more(さらに言うと)
- in addition(加えて)
- by the way(ところで)
- oh, and(あ、そういえば)
3️⃣ 話題を展開・転換する(流れを変える)
- actually(実は)
- in fact(実際のところ)
- as a matter of fact(実を言うと)
- anyway(とにかく/話を戻すと)
- well(ええと/そうですね)
- you know(ほら/わかるでしょ)
4️⃣ 理由・結果を説明する(because系)
- that’s because〜(それは〜だからです)
- so / therefore(だから)
- as a result(その結果)
- that’s why〜(だから〜なんです)
5️⃣ 自分の意見を言う・補強する(意見提示)
- I mean(つまり/要するに)
- in my opinion(私の意見では)
- personally(個人的には)
- from my point of view(私の見方では)
- the thing is〜(問題は〜なんです)
6️⃣ 相手に共感・反応する(リアクション)
- right(そうですよね)
- exactly(その通りです)
- I see what you mean(言いたいことはわかります)
- that’s interesting(それは面白いですね)
- oh, really?(本当ですか?)
これらの表現は、いわば会話の潤滑油です。日本の教科書ではあまり扱われませんが、英語圏のスピーカーは一文ごとにこうしたフレーズを自然に挟んでいます。
たとえば、
“Well, actually, I agree with you, but for example, in my country…”
(そうですね、実は私もあなたの意見に賛成なのですが、例えば私の国では…)
このように、つなぎ表現を使うだけで会話が格段に自然になります。
話を続ける力=「会話維持力」は、スピーキング上達の最終段階とも言えます。文法の正確さよりも、“話を続けられる力”を重視する意識が、英語を“勉強”から“運用”へと変えていくカギです。
原因④ フィードバックを受けていない
スピーキングの上達にはフィードバックが不可欠
英語スピーキングの学習では、「話すこと」そのものに意識が向きやすく、自分の発話を“振り返る時間”が取れていない学習者が非常に多いです。しかし、どんなトレーニングでも、フィードバックなしでは上達の方向性が定まりません。自分がどこでつまずいているのか、何を改善すべきなのかがわからないまま練習を重ねても、「量はこなしているのに伸びない」という結果に陥ってしまいます。
スピーキングの改善には、自己認識が不可欠です。プロのアスリートがフォームを動画で確認するように、英語学習者も自分の発話を見直すことで初めて、課題を“見える化”できます。つまり、「話す」だけで終わらせず、「どう話しているか」を分析することが成長の出発点なのです。
AI分析を取り入れて改善ポイントを見える化
人間の感覚だけで自分の英語を評価するのは難しいものです。「今日はうまく話せた」と思っても、録音を聞いてみると意外に文法ミスが多かったり、逆に「全然話せなかった」と感じた回が、実は流暢さの面では向上していたりします。このように、主観的な印象と実際のパフォーマンスにはギャップがあります。
そのため、スピーキング上達の第一歩は、客観的な視点で自分の話し方を知ることです。録音を聞き返す、教師やAIからフィードバックをもらうなどの方法を通じて、「文法」「語彙」「発音」など、どの要素が弱点なのかを明確にしましょう。AIアプリを使えば、録音した音声をもとに文法エラーを自動で訂正してくれます。
また、AIのフィードバックは「ネガティブな指摘」ではなく、「どの部分が改善すればもっと自然に聞こえるか」を具体的に示してくれます。これを継続的に利用することで、自分では気づかない発話のクセや弱点を修正でき、練習の精度が飛躍的に上がります。
「感覚的な練習」から「データに基づく練習」へ。これが今の時代のスピーキング上達法です。
イチオシは「初めてのAIスピーキング」です。第二言語習得理論に基づいた設計で、着実にスピーキング力を向上させていけます。
原因⑤ 学習サイクルが確立していない
練習した内容を振り返らず“やりっぱなし”にしない
多くの学習者は、英語を「勉強して終わり」にしてしまっています。今日やったことを振り返らず、次の日には新しい教材へ。こうした“やりっぱなし”の学習では、成長の軌跡が見えず、結果的に「頑張っているのに伸びない」という停滞感に陥ります。スピーキングは一度練習して終わるものではなく、繰り返しと修正を伴うプロセス型のスキルです。
上達する人ほど、練習後に「何ができたか」「どこで詰まったか」を丁寧に振り返ります。その積み重ねが、次の練習での改善点となり、成果の再現性を生み出します。つまり、“練習→振り返り→再挑戦”のサイクルを回せる人が最短で伸びるのです。
「記録→分析→再挑戦」の仕組みを作る
上達の鍵は、単発的な練習ではなく「仕組み化」です。自分の発話を録音し、分析して、再度同じテーマで話すというサイクルを確立できれば、毎回の練習が確実に次につながります。このようなスピーキング・ループを作ると、成長が目に見える形で蓄積されていきます。
実際、AIスピーキングアプリや学習ノートを活用して「話した回数・時間・語数」を記録するだけでも、自分の変化を実感しやすくなります。最初は10秒しか話せなかったテーマが、1か月後には1分話せるようになっていたといった“進歩の見える化”こそが、継続と上達を生む最大の原動力です。
今すぐできる改善法5選

改善法① “話すためのインプット”に切り替える
音読・シャドーイングで口に出せる英語を増やす
スピーキングを伸ばすための第一歩は、「読む・聞く」インプットを「話す前提のインプット」に変えることです。多くの学習者は、英文を理解することに集中しすぎて、“口に出せる英語”を増やす練習をしていません。音読やシャドーイングは、脳と口を同時に動かすことで、理解した英語を発話に転換する回路を育てます。文章の構造やリズムを体に染み込ませるように繰り返すと、英語を組み立てるスピードが格段に上がります。
特に効果的なのは、短く自然な会話文を毎日声に出すことです。ネイティブ音声のあとに続けて発話する「リピーティング」や、同時に声を重ねる「シャドーイング」は、発音・イントネーション・リズムを一度に鍛えられる効率的な方法です。リスニング教材を“声を出すトレーニング”に変えることで、インプットとアウトプットの境界がなくなり、学んだ英語がそのまま「話す力」として使えるようになります。
「使える素材」を厳選して短時間で繰り返す
スピーキング上達には、教材の数よりも「使う回数」が重要です。一つの素材を繰り返すことで、英語表現の構文や語順が脳内に自動化され、“考えなくても言葉が出る状態”が作られます。この自動化こそが、流暢に話せる人の共通点です。
素材を選ぶ際は、自分のレベルより少し易しく、内容が具体的なものを選びましょう。理解できる素材を繰り返すことで、「英語で考える」処理回路が形成されます。学習時間を1日15分に絞っても構いません。同じフレーズを5回声に出す方が、異なる教材を1回ずつやるよりも確実に効果があります。“繰り返しによるスキル化”を意識することが、スピーキング力を定着させる最短ルートです。
改善法② 1日5分の“独り言トレーニング”を始める
日常の行動を英語でつぶやく
スピーキング練習というと、相手がいないとできないと思われがちですが、実は「独り言」はもっとも身近で効果的なトレーニングです。たとえば、朝の支度をしながら “I’m brushing my teeth.” “I have to leave soon.” のように、今していることを英語でつぶやくだけで、英語で思考する習慣が自然に身につきます。
このトレーニングの狙いは、正確な文法よりも瞬時に言葉を組み立てる力を鍛えることです。日本語を介さず、目の前の状況を英語で説明する練習を繰り返すうちに、「考える→訳す→話す」という回り道が短縮され、英語で直接発想する回路が育ちます。慣れてきたら、“What should I eat today?” “Maybe I’ll cook pasta.” のように、思考そのものを英語化していくとさらに効果的です。
独り言を活用したスピーキング練習は別記事で詳しく解説しています。
思考回路を鍛え、発話をスキル化する
スピーキング力とは、声や筋肉の問題ではなく、思考プロセスを自動化するスキルです。話すたびに「文法」「語彙」「語順」を頭の中で確認していては、会話のテンポが止まってしまいます。毎日5分でも独り言を継続することで、脳が「英語で考えて英語で反応する」処理ルートを作り始めます。これは筋肉を鍛えるのではなく、思考回路を再配線するトレーニングです。
短い時間でも、繰り返すことで徐々に発話が自動化されていきます。最初はつまずいても、続けるうちに“無意識で口が動く瞬間”が訪れます。その状態こそ、スピーキングが「知識」から「スキル」に変わったサインです。英語を日常の思考言語に近づけるために、小さく・頻繁に・継続的に英語で話す環境を自分で作りましょう。
改善法③ “録音→聞き返す”を習慣にする
自分の発話を客観的に分析する
英語スピーキングの上達には、「話す練習」と同じくらい「聞き返す時間」が重要です。自分の声を録音して聞くことで、普段は気づかない弱点が驚くほど明確になります。「思っていたより間が長い」「単語の繰り返しが多い」「文が途中で途切れている」など、実際に聞いて初めて見えてくる課題がたくさんあります。
この“セルフレビュー”の目的は、自分を責めることではなく、現状を客観視することです。録音を聞きながら、良かった点・改善点を一つずつメモに取るだけでも、漠然とした「話せない感覚」が、明確な“改善リスト”に変わります。この積み重ねが、自己成長を実感できる「学習の手応え」につながります。
AIアプリで自動フィードバックを活用
最近では、AIスピーキングアプリを使えば、録音データから自動で発音・語彙・文法などを分析できます。特に便利なのは、客観的な改善ポイントの提示です。英会話スクールに通っていても講師が逐一訂正してくれるケースは稀ですが、AIなら「どの単語を間違えたか」「どの部分で詰まったか」を瞬時に可視化してくれます。
こうしたツールを使うことで、練習が「なんとなくの努力」から「データに基づく改善」へと変わります。毎回のデータを比較すれば、自分の成長が見えるため、モチベーションも維持しやすくなります。重要なのは、AIの指摘を“正解・不正解”として受け取るのではなく、「次はここを直してみよう」という具体的行動に変えることです。テクノロジーを上手く取り入れれば、独学でもプロフェッショナル並みの練習サイクルを作ることができます。
改善法④ “使えるフレーズ”を場面ごとにストックする
英語をスムーズに話せる人ほど、即興で完璧な文を作っているわけではありません。実は、よく使う「型」や「フレーズ」をストックしているのです。中でも汎用性が高いのが、「意見+理由」の構文です。たとえば、次のようなフレーズを持っておくだけで、会話の中で迷う時間が激減します。
- I think it’s important because…(〜は大切だと思います。なぜなら…)
- In my opinion, it helps people to…(私の意見では、それは人々が〜する助けになります。)
- I prefer A to B because〜.(BよりもAのほうが好きです。なぜなら〜。)
- One reason is that〜.(その理由のひとつは〜だからです。)
このような“話の枠”を持っておくだけで、発話時の思考負荷が大きく下がり、「意見を言う→理由を添える」という流れが自動化されていきます。これは英検面接や日常会話、ビジネスディスカッションなど、あらゆる場面で通用する基本スキルです。最初は3〜4種類の型を徹底的に繰り返し使い、英語で考える思考ルートを定着させましょう。
日常・試験・仕事などシーン別に整理する
フレーズを効率的に覚えるコツは、シーンごとに分けて整理することです。たとえば、以下のように使う場面を意識して分類すると、必要なときにすぐ取り出せます。
💬 日常会話で使えるフレーズ
- That sounds great.(それはいいですね。)
- I’m not sure.(よくわかりません。)
- By the way,〜(ところで〜)
🗣 試験・スピーチで使えるフレーズ
- First of all,〜(まず初めに〜)
- For example,〜(たとえば〜)
- In conclusion,〜(結論として〜)
💼 仕事・ビジネスで使えるフレーズ
- I’d like to suggest that〜.(〜を提案したいと思います。)
- Let’s discuss this further.(この件についてさらに話し合いましょう。)
ノートやアプリで「フレーズ帳」を作り、自分がよく使う状況を想定して整理すると効果的です。単語を覚えるだけでなく、文のまとまりとして“使う前提”で練習することが大切です。フレーズを記憶して終わりにせず、声に出して反射的に出てくるまで繰り返しましょう。これが「記憶」から「即応」への転換を生み、スピーキングを自動化するカギになります。
改善法⑤ “スピーキング・ループ”を作る
1回の練習を「話す→振り返る→言い直す」で完結させる
多くの人は、スピーキング練習を「一度話して終わり」にしています。しかし、実際に上達する人は、一つのタスクを短いサイクルで繰り返す習慣を持っています。たとえば、同じトピックで次のように進めてみましょう。
- 1回目:自由に話す(制限時間を決めて話す)
- 2回目:録音を聞いて改善点を整理する(文法・語彙・テンポをチェック)
- 3回目:言い直す(改善を意識して再度話す)
この3ステップを行うだけで、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目のほうが滑らかになります。重要なのは、“完璧な英文を作ること”ではなく、“前より良く話すこと”です。短時間でも繰り返すことで、脳がエラーを修正し、発話がスキルとして自動化されていきます。このループを回すたびに、「自分の中で話せる英語の回路」が着実に増えていくのです。
週単位で“見える成果”をチェックする
学習を続けるには、「自分がどれだけ成長したか」を定期的に確認することが欠かせません。週ごとに練習内容を振り返り、次のような変化をチェックしてみましょう。
- 前よりも長く話せた
- 詰まる回数が減った
- 発音やイントネーションが安定した
こうした具体的な変化をノートやアプリに記録すると、“成長の実感”が得られます。AIスピーキングアプリを使えば、発話時間・語数・スコアの推移が自動で記録され、「話す→確認→改善→再挑戦」のサイクルを週単位で回すことができます。
スピーキングは努力量が見えにくいスキルですが、記録を取ることで「確かに前より話せている」と感じられるようになります。この学習ループを仕組み化できる人こそ、停滞期を抜けて確実に伸びていくのです。
まとめ 〜停滞期は「伸びる前のサイン」〜
- スピーキング力は「練習 → 振り返り → 再挑戦」の積み重ねで伸びる
- 一度話しただけでは“使える英語”にならない
- 今日紹介した5ステップを続ければ、確実に変化を実感できます
英語スピーキングが伸び悩むのは、努力が足りないからではありません。むしろ、それは上達の直前に現れる自然なサインです。大切なのは、焦らずに学習サイクルを回し続けること。「話す → 録音する → 振り返る → 言い直す」というプロセスを習慣化できれば、どんな学習者でも、必ず“話せる英語”へと近づいていきます。
もし自分一人では継続が難しいと感じる場合は、AIが自動でフィードバックを返してくれる「初めてのAIスピーキング」を活用してみてください。このアプリでは、録音した英語を瞬時に分析し、文法や表現を自然な形に訂正してくれます。発話内容に合わせて改善アドバイスも提示されるため、「話す → 振り返る → 再挑戦する」流れをアプリ上で自動的に実現できます。
忙しい人でも1日5分から始められ、英検対策から日常英会話まで幅広く対応。あなたのスピーキング練習を“可視化”し、継続できる仕組みを提供します。
実際に私も利用していますので、詳しくは別記事でレビューしています。
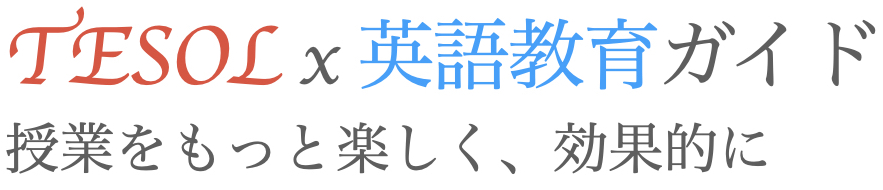






















ASAKOROKO
長年にわたり英語教育と試験対策に携わり、英検対策授業やAIを活用したスピーキング練習支援の研究を行っています。学習者一人ひとりが自宅でも効率よく学習を進められるよう、実践的かつ科学的な学習法の紹介を心がけています。