英検準2級プラスは、2025年度第1回から新設された 準2級と2級の“あいだ”を埋める橋渡しの級です。英検協会の分析では、準2級から2級まで平均18か月〜2年かかると言われ、ここで学習が停滞しがちでした。そこで登場したのが準2級プラスです。
この記事では、難易度・CEFRレベル・配点(CSEスコア)を一目でわかるように比較し、準2級プラスのライティング(要約+意見)や面接(3コマのストーリー描写+理由説明)など、2級につながる“実践型タスク”のポイントを整理します。語彙の目安や合格ラインの考え方も具体的に提示し、「準2級→準2級プラス→2級」の最短ルートを提案します。
「今、自分は準2級プラスを受けるべき?」という悩みにも、学習者タイプ別の指針で明確に回答していきます。効率よく、英語力を伸ばしていきましょう。
英検準2級プラスとは?2025年度から新設された新しい級
2025年度第1回検定より、「英検準2級プラス」が新たに加わりました。この新設級は、従来の準2級と2級のあいだに位置づけられ、高校卒業時の到達目標とされる2級(CEFR B1)に向かう過程を、より段階的に進められるよう設計されています。

英検協会の分析によると、準2級に合格してから2級に到達するまでには、平均で約18か月から2年程度かかるとされています。これは、他の級の間隔(例えば3級から準2級へ約1年前後、2級から準1級へ約1年半前後)に比べても長く、多くの受験者が「準2級から2級の間で停滞しやすい」ことを示しています。
そのため、2級に挑戦することなく学習をやめてしまう学生も少なくありませんでした。準2級プラスは、こうした背景を踏まえ、学習者のモチベーション維持と段階的なステップアップという教育的意図から新設されました。
準2級プラスの難易度と合格点

準2級プラスの難易度
語彙レベルの差
英検準2級プラスでは、語彙の難易度も準2級より一段階上がります。準2級が「日常生活の基本的語彙」を中心とするのに対し、準2級プラスでは「学校・地域・社会的テーマ」など、少し広い範囲の話題が扱われます。
目安となる語彙数は、準2級がおよそ 2,600〜3,000語、準2級プラスは 3,000〜3,500語前後です。高校英語の前半(高1〜高2程度)で学ぶ語彙が中心で、社会・環境・健康・テクノロジーなど、抽象度がやや高いトピックも登場します。一方で、2級(約4,000〜5,000語)ほどの難語は出題されないため、実用的で到達しやすい中間レベルといえます。
実際に3000語レベル以上の語彙比率を分析された方がいらっしゃいますが、みごとに階段状になっています。
語彙対策は必須ですので、単語帳などを用意されることをオススメします。
そのほかの対策教材についても、別記事で詳しく解説しています。
問題形式の違い(ライティング)
準2級プラスでは、出題形式にもライティングとスピーキングを中心に大きな変化があります。
準2級では「メールへの返信+意見文」でした。準2級プラスでは2級と同じ「要約+意見文」形式に変更されました。要約問題では、約80語の英文を25〜35語にまとめます。意見文では、準2級と同様に自分の意見を50〜60語で記述します。
要約問題は準2級までにはない出題となりますので、対策が必須です。ライティング問題の対策は別記事にしています。
出題形式の違い(面接)
面接(2次試験)は、準2級の「絵の描写」から、3コマのストーリー形式に変わりました。受験者は、登場人物の行動や発言を過去形で説明し、吹き出しにあるセリフや状況をもとに物語の流れを説明します。さらに、後半の質問では自分の考えや理由を述べるタスクが含まれます。
こちらも対策が必須です。スピーキングが苦手な場合は、1次試験終了後すぐにでも取り組むことをオススメします。面接対策は別記事にしています。
準2級プラスの体感難易度
準2級プラスはまだ新設されたばかりで公式な合格率データは限定的ですが、受験者の体感では「準2級より難しい」という評価が多く見られます。体感的にも準2級以上であることは間違いないようです。
出題方式と合格目標点
準2級プラスの出題形式
準2級プラスの出題方式は、次の通りです。
■リーディング:短文の語句空所補充(17問)
■リーディング:長文の語句空所補充(6問)
■リーディング:長文の内容一致選択(Eメール:3問、説明文:5問)
■ライティング:要約問題(1問)
■ライティング:意見論述問題(1問)
■リスニング:会話の応答文選択(15問)
■リスニング:文の内容一致選択(15問)
準2級プラスの合格点
CSEスコアでは 1829 点が合格点となっていますが、素点ベースで何点取れれば合格できるのか気になりますよね。最低限の目安としては次の通りです。
- リーディング 19 / 31点
- ライティング 19 / 32点
- リスニング:18 / 30点
- 合計 56 / 93点
実際には数点の変動はありますので、余裕を持って得点できるよう対策しておくのが望ましいです。
準2級とプラス、どちらを受けるべき?

英検準2級プラスの導入によって、「準2級の次にプラスを受けるべきか、それとも一気に2級を狙うべきか」と悩む学習者が増えています。結論から言えば、どちらを選ぶかは目的と現時点の英語力によって異なります。
準2級プラスは「英語を使って考え、伝える力を養う中間ステップ」として設計されており、すぐに2級を目指すのが不安な人には効果的なルートです。一方、すでに基礎が十分に固まっていて、2級レベルの長文や抽象的なテーマにもある程度対応できる人は、プラスを飛ばして直接2級に挑戦しても構いません。
準2級プラスが向いている学習者タイプ
高校生・専門学校生・社会人初級者の目安
英検準2級プラスが最も力を発揮するのは、「準2級までは順調に進んだが、2級にはまだ不安がある」という層です。たとえば次のような学習者が典型的です。
- 高校生・専門学校生:学校の授業や定期試験で準2級レベルの内容は理解できるが、2級の英文では語彙が難しく、文章が長いと感じる。
- 大学受験を意識し始めた高校2年生:文法力やリーディング力はあるものの、英語で意見を書いたり話したりする力がまだ発展途上。
- 社会人初級者:仕事や旅行で英語を使いたいが、2級の抽象的な話題(環境・経済・国際問題など)には自信がない。
このような層にとって、準2級プラスは「自分の考えを英語で短くまとめる」訓練を通じて、準2級で止まっていた学習を再始動させる実践的な目標になります。
語彙や文法のレベルは大きく上がりませんが、「要約」「理由説明」「意見表現」といった2級に必要な力を段階的に育てることができます。
2級へのステップとしての戦略的受験
準2級プラスを受ける最大のメリットは、2級を目指すための足場を固められることです。2級では、要約・意見ライティング・社会的テーマの理解など、思考型の出題が中心になります。準2級プラスで一度この形式を経験しておくと、2級受験時に「形式の慣れ」「語彙運用の幅」「英文構成力」のいずれも格段にスムーズになります。
実際、多くの学習者が「準2級に合格したあと2級を受けるまでに1年以上かかった」と感じており、モチベーションを維持するうえでも“中間ゴール”があることは大きな意味を持ちます。
ただし、すでに2級の過去問をある程度読める・書けるレベルに達している人や、大学入試で2級以上のスコア換算を狙う人は、準2級プラスを経由せず直接2級へ進む方が効率的です。
詳しくは別記事で解説しています。
効率的なステップアップの順序【準2級→準2級プラス→2級】
英検の各級を「連続したステップ」としてとらえると、最も効率的なのは準2級 → 準2級プラス → 2級 という順序です。これは単に難易度順というだけでなく、学習内容とスキルの発展順にも沿った理にかなった進み方です。
準2級で身につける「基礎文法・日常語彙・短文理解」は、英語学習の土台になります。
準2級プラスでは、その知識をもとに「要約・意見表現・理由説明」などの発信スキルが加わり、2級ではさらにそれを発展させて「社会的テーマに関する論理的表現」へとつながります。
学習期間とスコア目標の設定
準2級から2級までは、多くの学習者が平均18か月〜2年ほどを要するといわれています。この期間を効果的に短縮するには、準2級プラスを中間目標として設定し、次のようなCSEスコアと期間の目安を意識するのが現実的です。
| 段階 | 目標スコア(CSE) | 学習期間の目安 | 主な課題 |
|---|---|---|---|
| 準2級合格 | 約1,720点 | スタート地点 | 読解・リスニング中心の基礎定着 |
| 準2級プラス合格 | 約1,980点 | 約8~12か月 | 要約・意見表現・スピーキングの強化 |
| 2級合格 | 約2,150点 | 約18~24か月 | 抽象的テーマでの発信・論理構成力 |
準2級プラスを経由することで、2級で求められるスキル(特にWritingとSpeaking)を事前に慣らしておけるため、結果的に最短ルートで2級合格に到達できます。また、「準2級→準2級プラス→2級」と段階を踏むと、合格体験による自己効力感が積み重なり、モチベーションを維持しやすくなります。
準2から2級まで約2年というのは、あくまでも平均です。詰め込めば短縮することは可能です。例えば、1日3時間以上、効率的にポイントを押さえていけば1年での到達も可能です。時間が限られる方は諦めずに挑戦することをオススメします。
効率よく実力を伸ばす学習ステップ
準2級プラスを活用した効果的な学習ステップは、次の3段階に整理できます。
① 基礎の再確認(リーディング・リスニング)
準2級レベルの文法・語彙を確実にし、短い英文を正確に理解する練習を繰り返します。単語は単語帳で補強したり、読解やリスニングは対策問題集を利用していきましょう。
② 要約力と意見表現のトレーニング(ライティング)
準2級プラスの要約問題(約80語→25〜35語)に慣れ、「短く・正確に言い換える」練習を重点的に行います。意見ライティングでは、「I think 〜. First ~. Second~」構文といった構成を軸に、自分の意見を1文+理由2文でまとめる練習を繰り返すと効果的です。
③ ストーリー説明と理由づけの練習(スピーキング)
準2級プラスの面接形式(3コマのストーリー描写)に合わせ、時系列・過去形・吹き出し引用を意識して話す練習を行います。1次試験を受けたらすぐに取り組むのがオススメです。
対策教材は別記事で紹介しています。合わせてご覧ください。
準2級プラスをCEFRとCAN-DOで分析

英検準2級プラスは、準2級よりは難しくなりますが、準2級と同じ CEFR A2 レベル です(公式資料参照)

このレベル帯は、CEFR A2+(発展段階) と表現することも可能です。A2(基礎段階)とA2+(発展段階)のCAN-DOを比較すると、次のようになります。
CEFR A2 基礎段階(準2級レベル)
身近で日常的な話題を理解し、簡単なやり取りができる段階。相手がゆっくり明確に話す場合に対応可能です。具体的には、次のようなことができます。
- 自分や家族、買い物、地理、仕事など、身近で優先度の高い話題に関する表現を理解できる。
- 簡単で直接的な情報交換が必要な場面で、短いやり取りができる。
- 自分の背景や身近な環境、日常生活について、簡単な語句で説明できる。
CEFR A2+ 発展段階(準2級プラス)
A2(基礎段階)よりも積極的にやり取りができ、助けを借りながら会話を維持できる。短い独話や簡単な説明が可能になります。具体的には、次のようなことができます。
- 身近な話題について、簡単な会話を始め・続け・終えることができる。
- 予測可能な日常的状況で、自分の考えや情報を交換できる(必要に応じて助けを得ながら)。
- 人・場所・日常生活・過去の出来事などを簡単な文で描写できる。
- 自分の好みや感情を説明し、出来事や経験を簡潔に語れる。
このように、A2基礎段階と比べると出来ることの幅が広がるものの、B1(中級・2級レベル)と比べるとその範囲は限定的です。参考までにB1のCAN-DOも掲載します。
CEFR B1(中級)
さまざまな場面で自立して意思疎通ができる。意見を述べ、理由や説明を加えられる。
- 旅行先や日常的な社会的状況など、幅広い場面で自分の意思を伝え、やり取りを維持できる。
- 自分の意見を述べ、理由を説明したり、簡単な主張を展開できる。
- 経験・夢・希望・計画などを説明し、意見や行動の理由を短く説明できる。
参考: COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT. (2020).
準2級プラスで注意すべき点
最後に、準2級プラス受験で注意すべき点です。
準2級プラスは CEFR A2 の試験です。満点をとって CSE スコアがどれだけ高くなっても判定は CEFR A2 です。
大学入試などは CSEスコアだけでなく、受験級を2級以上としている場合も少なくありません。受験への利用を考えている場合には注意が必要です。
あくまでも学習のための、2級に向けた中間成果を図るための受験、との位置付けにしておくのが無難です。
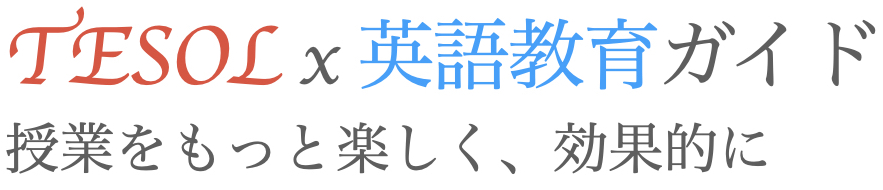



















ASAKOROKO
長年にわたり英語教育と試験対策に携わり、英検対策授業やAIを活用したスピーキング練習支援の研究を行っています。学習者一人ひとりが自宅でも効率よく学習を進められるよう、実践的かつ科学的な学習法の紹介を心がけています。