「読み書きはなんとかなっても話せない」というのは、多くの英語学習者がぶつかるこの壁です。原因は「努力不足」ではなく、インプットからアウトプットへつなぐ学習設計の欠如にあります。 本記事では、第二言語習得理論とAI時代の学習環境をかけ合わせ、「英語を“自分の言葉”として話せるようにする」ためのステップを、科学的根拠とともに解説します。
著者は、英検1級保持・英国大学院修士(TESOL/英語教授法)修了の現職大学教員です。長年にわたり英語教育とスピーキング指導に携わり、現在はAIを活用した自宅スピーキング練習の研究も行っています。単語暗記や音読・シャドーイングだけで終わらせず、「使える英語」を設計的に育てるための戦略を、教育現場と研究の両視点からお届けします。
この記事では、次の3ステップで「科学的に効果的な英語スピーキング勉強法」を体系的に紹介します。
- インプットからアウトプットの流れを最適化する
- 英語を上手に話すコツと実践トレーニング方法
- よくある間違った勉強法(やりがちNG)
スピーキング力は、「努力」ではなく「仕組み」で伸ばす時代です。理論に裏づけられた正しい順序とAIの力で、あなたの英語を“使えるスキル”へ変えていきましょう。
INDEX
- インプットからアウトプットの流れを最適化する
- 英語を上手に話すコツと実践トレーニング方法
- 実践トレーニングの場をつくる
- よくある間違った勉強法(やりがちNG)
- まとめ — これからはAIアプリがイチオシ
インプットからアウトプットの流れを最適化する
適切なインプットを確保する
必要な語彙と文法を学ぶ
英語を「話す」には、まず語彙と文法という土台が不可欠です。どれほどスピーキング練習を重ねても、使いたい言葉を知らなければ表現できません。
また、単語を並べるだけでは意味のつながりが曖昧になり、伝えたい内容が正確に届かないこともあります。語彙は「意味を運ぶ材料」、文法は「それを組み立てる仕組み」です。この二つが揃って初めて、メッセージとして機能します。
第二言語習得研究でも、語彙・文法力はスピーキング能力の発達において中核的な役割を果たすとされています。
Bachman & Palmer(1996)が提唱した言語運用能力モデルでは、コミュニケーション能力は「文法的知識」と「語彙的知識」に支えられると明示されています。この理論は英語教育の基礎となり、今日でも多くの教材開発やAIスピーキング評価システムに活かされています。
要するに、スピーキング練習を積む前に、「自分が使える語彙」と「直感的に組み立てられる文の型」を一定量確保しておくことが、後の流暢な発話を支える出発点になるのです。
今より少し上のレベルに挑戦する
言語習得の世界では、Krashen(1982)による「インプット仮説」が非常に有名です。これは、人が新しい言語を学ぶとき、“自分の現レベルより少し上の英語(i+1)”に触れることが最も効果的だという理論です。
簡単すぎる教材では脳が「処理の自動化」に入ってしまい、成長が止まります。逆に難しすぎると理解できず、学習効率が下がってしまいます。
この「ちょっと上の英語」を見極めるためには、理解度7〜8割を目安にするのが理想です。AI教材を使えば、レベルや語彙の出現頻度を自動で調整できるため、まさに「自分専用のi+1インプット環境」を構築できます。
また、Vygotsky(1978)の「最近接発達領域(ZPD)」の考え方もここに通じます。これは、学習者は、単独ではできないタスクでも、少しの支援(例:字幕・ヒント・例文提示)を受けることでより高いレベルの言語処理が可能になるというものです。この「適度な負荷」を継続的に与えることが、スピーキング力の成長曲線を押し上げるポイントです。
理解できる英語にほんの少しの挑戦を加え続ける――それが、受動的な学習を能動的な運用力に変える、科学的にも実証された方法です。
基礎トレーニング(インテイク)を欠かさない
英語を聞いて理解するだけでは、まだ「自分の言葉」として使える段階には到達しません。理解したインプットを実際の発話に結びつけるためには、繰り返しによるスキル化が必要です。その理論的な枠組みを与えているのが、Anderson(1983, 1993)のスキル習得理論です。
この理論によれば、言語の運用能力は「知識」として理解するだけでなく、それを使う練習を通じて自動化することで初めて定着します。学習者は以下の3段階を経て、英語を“考えずに使える”状態へと近づきます。
- 認知段階(Cognitive stage):文法や語彙のルールを理解する段階。
- 連合段階(Associative stage):練習を重ねるうちに誤りが減り、処理がスムーズになる段階。
- 自動化段階(Autonomous stage):意識せずに瞬時に使えるようになる段階。
この「知識の自動化」を促すトレーニングが、音読とシャドーイングです。
音読で口から英語が出る習慣を作る
音読は、文字として理解している英語を口の運動と結びつける訓練です。声に出して読むことで、文の構造や語順をスキルとして脳に刻み込みます。
最初は「考えながら読む」認知段階ですが、同じ文を何度も繰り返すうちに、構文や発音パターンが自動化され、文法を意識しなくても自然に話せるようになります。
例えば “I’d like to〜” や “There is〜” のような構文は、音読を通して「反射的に口から出る」形で定着していきます。このプロセスこそ、Andersonの理論でいう自動化そのものです。
また、音読には心理的な利点もあります。声に出すことでリズムとイントネーションの感覚が育ち、「文を読む」のではなく「意味を伝える」感覚に変わっていくのです。この“思考と言葉の一体化”が、スピーキングの基盤を作ります。
シャドーイング
シャドーイングは、聞こえた音声をほぼ同時に再現する訓練です。もともとは通訳士養成のトレーニングです。最初は聞き取るだけでも難しく感じますが、繰り返すうちに脳が英語の音とリズムのパターンを予測できるようになります。
シャドーイングでは、聞く・理解する・発話するという複数の処理を同時に行うことで、英語の処理速度が格段に向上します。
この段階で重要なのは「正確さより継続」です。1回の完璧な練習よりも、5分でも毎日繰り返すことで、脳が「英語の音とリズムを即座に再現する」神経経路を作ります。
アウトプットを必ず行う
アウトプットが必要な理由
英語が「使える」ようになるには、インプットやインテイク(音読やシャドーイング)だけでは不十分です。音読やシャドーイングで英語の音や語順、表現パターンを体に覚え込ませたら、次のステップはそれを自分の言葉として使ってみることです。
たとえば、練習で覚えたフレーズを使って「昨日の出来事を説明する」「自分の考えを英語で言ってみる」など、自分自身の話題を題材にしたアウトプットを繰り返すと、記憶が定着し、表現が自然になります。
Bygate(2001)やSkehan(1998)の研究では、学習者が「自分に関係のある内容」について話す練習を重ねると、英語の流暢さ・正確さ・表現の幅がバランスよく伸びることが報告されています。
また、Swain(1985)はアウトプット仮説を提唱しています。これは、学習者が実際に言語を使って「表現しようとする」過程で、初めて自分の言語知識の不足に気づき、そのギャップを埋めようとすることで、文法的正確さが発達するというものです。
つまり、音読やシャドーイングで“英語の材料”を取り込み、それを自分の意見や経験の中で“使って試す”ことで、英語は初めて本当の意味で身につきます。
モニタリングを習慣化する
アウトプットの効果を最大化する1つ目の鍵は、モニタリング(monitoring)です。自分の発話を録音して聞き直したり、教師のフィードバックを受けたりすることで、「何が伝わったか」「どこで詰まったか」「どの表現を直すべきか」を客観的に把握できます。
第二言語習得におけるスピーキングの評価モデルでは、スピーキング能力を次の3つの観点から捉えます:
- 流暢さ(Fluency):テンポよく話せているか。沈黙や言い直しが多すぎないか。
- 正確さ(Accuracy):文法・語彙の誤りがどれくらい少ないか。
- 複雑さ(Complexity):どの程度、構文や語彙の幅を使いこなせているか。
これらは互いに影響し合う要素であり、流暢さ → 正確さ → 複雑さの順に発達していくとされています(Skehan, 1998)。そのため、一度にすべてを完璧にしようとするのではなく、何度も挑戦しながら少しずつバランスを取るのが効果的です。
AIアプリを使えば、発話スピード(流暢さ)や誤り検出(正確さ)を自動で可視化でき、人間では難しい定量的なモニタリングが可能になります。この「見える化」によって、学習者は自分の成長を実感しやすくなり、継続のモチベーションも高まります。
自分に合ったトピックで練習する
スピーキングの実戦力を高める2つ目の鍵は、自分が実際に話す可能性の高いトピックを選ぶことです。「旅行」「学校生活」「仕事」「趣味」など、自分の現実的な言語使用場面をもとに練習すると、実践的コミュニケーション力が高まります。
第二言語習得においても、他者のことや教科書の登場人物について話せるようになっても、それはあくまで「模倣されたコミュニケーション」にとどまり、実際の運用能力には結びつきにくいことが多いと指摘されています(Bygate, 2001)。
同じタスクを繰り返す(タスク・リピティション)
英語スピーキングの上達3つ目の鍵は、同じ話題を繰り返し話す練習(Task Repetition)です。一度きりの練習よりも、同じ内容を何度か話すことで、英語が自然に口から出やすくなります。
たとえば、Lambert ら(2017)は、日本人大学生が同じスピーキングタスクを繰り返した研究で、回を重ねるごとに発話速度が上がり、ポーズや言い直しが減るなど、流暢さが大きく改善することを確認しました。
また、Bygate(2001)や Bui & Ahmadian(2012)も、タスクの繰り返しによって文法の正確さが高まり、学習者が「意味」と「文法」の両方に注意を向けられるようになると報告しています。
これらの研究からわかるのは、タスクの繰り返しは単なる「慣れ」ではなく、英語の処理を自動化する練習法だということです。最初の2〜3回で話すスピードが伸び、その後の反復で文法や表現の正確さが安定していく傾向があります。さらに、1週間ほど間隔をあけて再び同じ話題に取り組むと、使う文構造の幅まで広がることが示されています。
同じテーマを何度か話すことが、英語を「考えながら話す」段階から「自然に出てくる」段階へと導く、非常に効率的な方法と言えます。
フィードバックで正確さを磨く
スピーキングの伸び悩みを打破する4つ目の鍵は、適切なフィードバックにあります。自分では気づけない文法や発音の誤りも、外部の視点によって初めて認識できます。
第二言語習得の研究では、Ellis, Loewen & Erlam(2006)などが、フィードバックが文法的正確さの改善に有効であることが確認しています。
AIスピーキングアプリでは、語彙の自然さ・文構造の誤りなどを即座に提示してくれるため、従来の「録音して終わり」の練習から一歩進んだ、個別の修正を伴うアウトプットが可能になり、学習が加速すると考えられます。
オススメのAIスピーキングアプリについては、別記事で解説しています。
英語を上手に話すコツと実践トレーニング方法

英語を「上手に話す」とは、完璧な文法で話すことではありません。言いたいことを、相手にわかりやすく、途切れずに伝えられることが大切です。ここでは、ネイティブスピーカーも実践している自然な話し方のコツと、効果的なトレーニング方法を紹介します。
口頭文法を理解する
口頭文法とは
スピーキングでは、書き言葉のように文法を厳密に整える必要はありません。むしろ、「話し言葉ならではの文法(口頭文法)」を理解し、柔軟に使えることが重要です。
たとえば、
“My hometown, it’s really small but beautiful.”
(私の故郷は、とても小さいけれども綺麗です。)
のように、主題(この場合は My hometown)を前に出して話すトピカライゼーション(topicalization)は、ネイティブの自然な口頭表現としてよく使われます。
反対に、文の最後に主題を付け足す「テイル構文(tails)」もよく使われます。次のようなものです。
“It’s nice, this place.”
(いいね、この場所)
そのほかにも、口頭では
“Can’t find it. — Oh, here it is.”
(見つかんないんだけど ーあ、ここにあった)
というように、書き言葉のような完全文でなく、意味のかたまりで発話されることもあります(Carter & McCarthy, 1995; Thornbury, 2005)
また、カジュアルな場面では、次のような省略もよく行われます。
“Want some coffee?”(=Do you want some coffee?)
コーヒーいる?(=コーヒーいかがですか?)
これらの英文は間違いではなく、「聞き手が理解しやすい構造」を優先した結果です。スピーキングをするときは、書き言葉における完璧さよりも「通じる英語」を意識し、言いたいことをシンプルに、順序よく伝えることを心がけましょう。
ネイティブも使う上手に話すコツ
フィラーを活用する
英語では、会話の間をつなぐフィラー(filler)が頻繁に使われます。“Well…”, “Let me think.”, “You know,” などの表現は、考える時間を稼ぎながら、会話のテンポを自然に保つ役割を果たします。
日本語でも「えっと」「そうですね」と言うように、英語でもフィラーはごく普通の会話技法です。フィラーを使うことで、沈黙を防ぎ、聞き手に「考えている」印象を与えられます。練習では、意識的にこれらを差し込む習慣をつけてみましょう。
特に英語では、日本語と違って沈黙を非常に嫌います。何かを考えているときは、考えていることがわかるよう、何か言わなければならないことも覚えておきましょう。
フォルススタートや自己訂正もOK
会話では、途中で言葉を間違えたり、別の表現を思いついて言い直したりすることがあります。これをフォルススタート(false start)と呼びます。
たとえば、
“I went to—well, actually, I was planning to go to—Tokyo last week.”
(行ったんだよね、えっと、実際のところは、行こうとしていたというか、東京に先週)
のように、文を途中で止めて修正する言い方です。このような言い直し(self-repair)やフォルススタートは、英語の自然な会話ではごく当たり前の現象で、ネイティブスピーカーも頻繁に使います。
言い換えれば、「一度で完璧に話す」ことよりも、話しながら整理していくプロセスこそが“生きた会話”なのです。止まってしまうよりも、「うーん、じゃなくて…」と話し続ける方が、聞き手にも「伝えようとしている」と伝わり、会話が自然に流れます。
実践トレーニングの場をつくる

スピーキング力を伸ばすには、知識を「使う場」が欠かせません。実際に声に出し、相手とのやりとりを通じて学んだ表現を確かめることで、英語が“使えるスキル”として定着します。
留学や短期研修で「使う」経験を積む
海外留学や短期研修などの「英語を使わざるを得ない環境」は、スピーキング力を一気に引き上げる最も効果的な方法の一つです。実際の会話では、教科書通りに進まないことがほとんど。だからこそ、自分の言いたいことを即興で組み立てる練習になります。
第二言語習得研究においても、実際に英語を「使う」経験は、単なる文法や単語の暗記よりも、記憶や理解を統合的に働かせるため、学習効果が高まることが指摘されています(Skehan, 1998)。
AIスピーキングアプリを活用する
留学が効果的なのはわかっても、実際のところ難しいですよね。ですが、AI技術を使えば同じような効果を得られます。AIスピーキングアプリでは、音声認識によってあなたの発話を分析し、文法や語彙のフィードバックを即時に受け取ることができます。
この「録音→評価→再挑戦」のサイクルを回すことが、まさにのスキル習得理論が示す“自動化”のプロセスにあたります。つまり、AIを相手に繰り返し練習することで、英語の処理スピードと自然な表現力が少しずつ定着していきます。
AI学習の強みは、いつでも、何度でも、失敗を恐れずに練習できること。継続すれば、留学と同じように「英語が自然に出てくる」段階に到達できます。
第二言語習得の分野でも、生成AIの利用に関する研究がすでに始まっています。Zou et al. (2023) は、自動フィードバック機能を備えたAIスピーチ評価システムが、学習者のスピーキング能力を有意に向上させることを明らかにしました。また、発話内容や話し方についても改善が見られたことを Cha et al. (2024) が報告しています。
AIスピーキングアプリのイチオシは、「初めてのAIスピーキング」です。300以上のトピックの中から、自分が話したい内容を選んで繰り返し練習できます。練習後にはAIが良かった点、文法の訂正、あなたの発話内容を取り入れた模範解答を生成してくれます。
これによって、「あ、こう言えば良かったんだ!」という学習がテンポよく進んでいきます。スピーキングをして、模範解答を見て、またスピーキングするというサイクルを自然と回せるので、効率よくスピーキングを上達させていくことができます。
詳しくは別記事でレビューしています。私も実際に使っていますので、ぜひご覧ください。
よくある間違った勉強法(やりがちNG)

スピーキング力を伸ばしたいのに、なかなか成果が出ない――。その原因は「努力不足」ではなく、「方法のミスマッチ」にあることがほとんどです。多くの学習者が陥りやすい“やりがちNG”パターンを整理しておきます。
よくある間違った勉強法①
単語帳と文法書だけで学習する(受験型)
単語や文法の暗記は大切ですが、それだけでは「話せるようにはならない」のが現実です。第二言語習得研究では、知識(knowledge)と運用(performance)は別の能力とされています(Bachman & Palmer, 1996)。つまり、知っている英語を実際に使う練習がなければ、会話でその知識を引き出すことはできません。
よくある間違った勉強法②
音読・シャドーイングだけで満足する(インプット偏重)
音読やシャドーイングは、語順感覚や発音を整える「インテイク(intake)」の段階として有効です。しかし、それを自分の言葉としてアウトプットする練習をしない限り、学習内容は“使える英語”として定着しません。理解で終わらせず、「自分の話題」で使ってみることが不可欠です。
よくある間違った勉強法③
オンライン英会話で話すだけ(修正がない)
オンライン英会話は実践の場として有効ですが、講師からのフィードバック(feedback)がないまま話すだけでは、誤りをそのまま繰り返してしまう恐れがあります。これを第二言語習得では化石化(fossilization)と呼びます(Selinker, 1972)。一度、化石化してしまうと訂正するのに時間がかかります。間違いはできるだけ早い段階で直した方がいいです。
よくある間違った勉強法④
受講生が多すぎて話せないグループレッスン
一度の授業で発話時間が数分しかないと、スピーキング力はほとんど伸びません。グループレッスンの理想的な人数は 12人程度までです。それより多くなると、学習者が発話する時間が限られてしまい、講師が中心となって進めるレッスンになることが多いです。スピーキングを伸ばすには良い環境とは言えません。
よくある間違った勉強法⑤
講師ばかりが話すレッスン
マンツーマンレッスンでは、あなたが7割話すのが理想です。講師のフィードバックに時間がかかる場合でも、6割以上はあなたが話すべきです。グループレッスンの場合でも、少人数で7割は学習者が話すべきです。
スピーキング力を伸ばすには、話す量も重要です。マンツーマンであっても、あなたが主役になって「発話の主導権」を持ちましょう。
よくある間違った勉強法⑥
定型文暗記型アプリの反復練習のみ
決まったストーリーや定型文を繰り返す練習は、文型を覚えるには役立ちます。しかし、それだけでは「自分の言いたいことが言えるようになる」保証はありません。なぜなら、学習内容と自分が実際に話したい内容が一致するとは限らないからです。
第二言語習得研究では、言語の習得は「形式」ではなく「意味」を中心に行われると考えられています。Long(1996)は、学習者は自分の考えを伝えようとする中で、初めて語彙・文法を“使える知識”へと変えていくと主張しています。
つまり、「誰かが決めた台本を正しく言う練習」ではなく、自分の意見・感情・経験をもとに表現する練習こそが、スピーキング力を根本から伸ばす鍵と言えます。
まとめ — これからはAIアプリがイチオシ

英語スピーキングは「知識」ではなくスキルです。だからこそ、正しい順番で“使う回数”を増やし、修正していく仕組みが勝ち筋です。
従来は難しかった個別のフィードバックや訂正も、生成AIのおかげで可能になりました。これらの英語学習は、間違いなくAIで加速していきます。
誤った学習に陥るリスクもないですし、時間を選ばず、いつでも好きなだけ練習できるのも魅力です。イチオシは「初めてのAIスピーキング」です。ぜひ使ってみてください。
参考文献
Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition. Harvard University Press.
Anderson, J. R. (1993). Rules of the mind. Lawrence Erlbaum Associates.
Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice: Designing and developing useful language tests. Oxford University Press.
Bui, G., & Ahmadian, M. J. (2012). Task repetition and second language speaking performance: The role of procedural repetition and strategic planning. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2(4), 379–406. https://doi.org/10.14746/ssllt.2012.2.4.3
Bygate, M. (2001). Speaking. Oxford University Press.
Carter, R., & McCarthy, M. (1995). Grammar and the spoken language. Applied Linguistics, 16(2), 141–158. https://doi.org/10.1093/applin/16.2.141
Cha, J., Han, J., Yoo, H., & Oh, A. (2024). CHOP: Integrating ChatGPT into EFL oral presentation practice. https://arxiv.org/abs/2407.07393
Ellis, R., Loewen, S., & Erlam, R. (2006). Implicit and explicit corrective feedback and the acquisition of L2 grammar. Studies in Second Language Acquisition, 28(2), 339–368. https://doi.org/10.1017/S0272263106060141
Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.
Lambert, C., Kormos, J., & Minn, D. (2017). Task repetition and second language speech processing. Studies in Second Language Acquisition, 39(1), 167–196. https://doi.org/10.1017/S0272263116000085
Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), Handbook of second language acquisition (pp. 413–468). Academic Press.
Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford University Press.
Selinker, L. (1972). Interlanguage. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10(3), 209–231. https://doi.org/10.1515/iral.1972.10.1-4.209
Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. M. Gass & C. G. Madden (Eds.), Input in second language acquisition (pp. 235–253). Newbury House.
Thornbury, S. (2005). Beyond the sentence: Introducing discourse analysis. Macmillan Education.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
Zou, B., Du, Y., Wang, Z., Chen, J., & Zhang, W. (2023). An investigation into artificial intelligence speech evaluation programs with automatic feedback for developing EFL learners’ speaking skills. SAGE Open, 13(3). https://doi.org/10.1177/21582440231193818
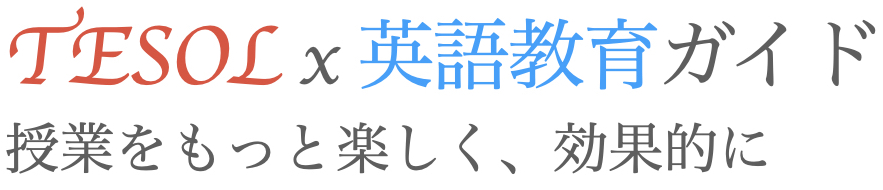











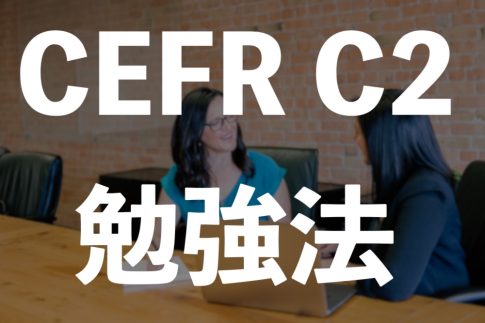













ASAKOROKO
長年にわたり英語教育と試験対策に携わり、英検対策授業やAIを活用したスピーキング練習支援の研究を行っています。学習者一人ひとりが自宅でも効率よく学習を進められるよう、実践的かつ科学的な学習法の紹介を心がけています。