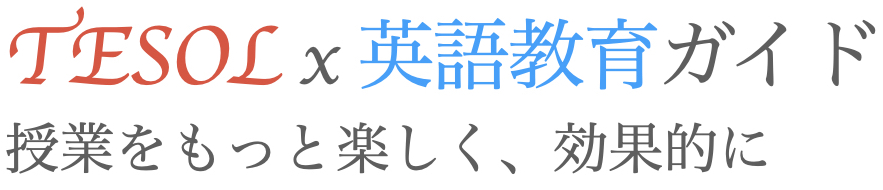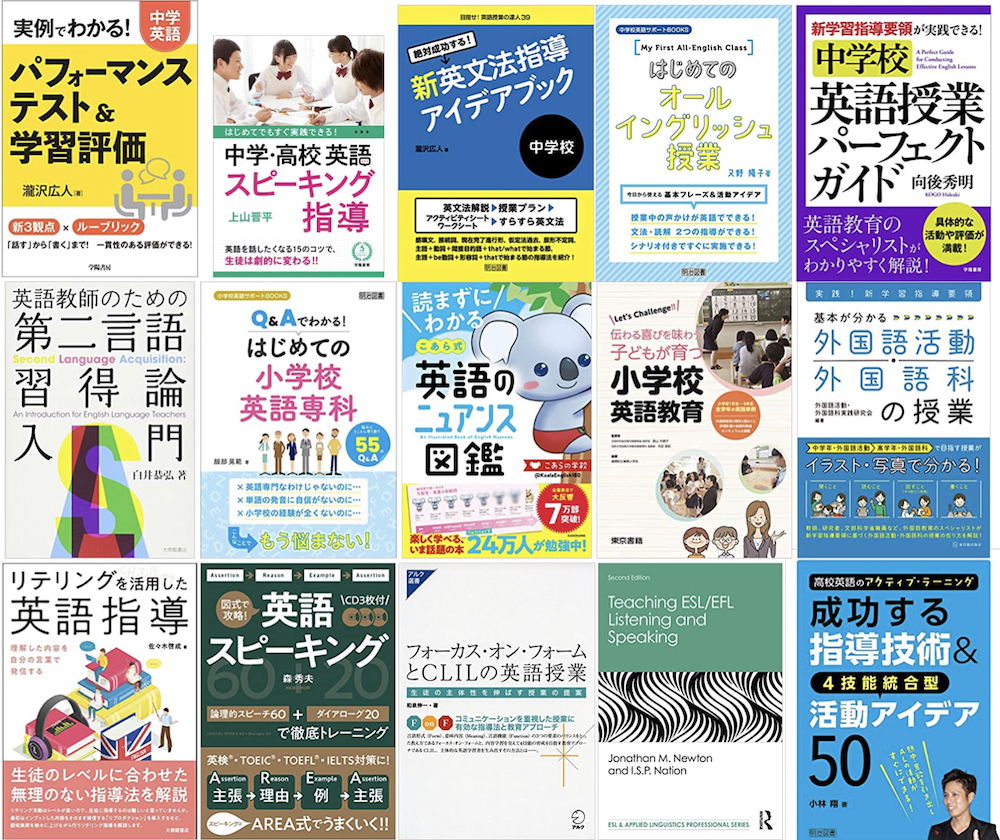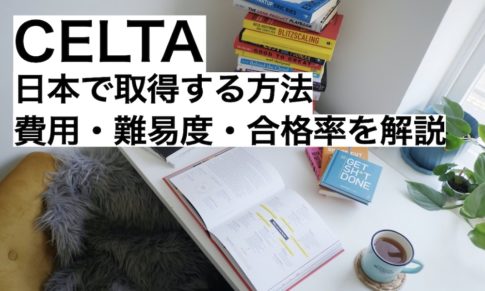大学や短期大学(短大)の教員というと、かつては「自由度の高い働き方」「研究ができる」というイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、実際の働き方は大きく変化してきており、ご自身が学生をされていたところと大きく変わっている可能性があります。授業の準備や成績評価だけでなく、学生指導、公務、さらには研究活動まで幅広い業務をこなさなければならず、自由に研究に没頭できる時間は限られています。
本記事では、大学・短大教員の働き方を「授業」「公務」「研究」「勤務時間」「将来性」という5つの観点から整理し、現状と課題を詳しく解説します。これから大学教員を目指す方や、教育現場の実態を知りたい方にとって有益な情報をまとめました。
大学・短大教員の授業業務

出席管理と成績評価
大学・短大教員の最も基本的な仕事は授業です。近年は出席管理や成績評価が厳格化しており、かつてのように「学生の自主性に任せる」スタイルは少なくなりました。また一時期はIC学生証を利用した出席管理もありましたが、管理の難しさから教員が氏名を呼び上げて出欠管理を行う学校まで出てきています。
特に短大では学生の生活習慣がまだ安定していないケースも多く、出席状況の把握や指導が欠かせません。また成績評価においても、明確なルーブリックや根拠を示すことが求められ、かつてのような教員裁量は減少しています。
オリエンテーションと最終試験
新学期のオリエンテーションでは、履修方法や単位取得のルールを学生に徹底する必要があり、学期の方向性を決める場となります。学生が春休みを過ごしている間にもシラバスの作成や教材の取り寄せなど教員はやることが山積みです。
さらに学期末には最終試験やレポート課題の実施・採点・成績登録といった業務が集中します。100人規模のクラスを複数担当している場合、採点作業は十数時間に及ぶことも珍しくありません。
昔と比べた自由度の減少
かつては「研究者としての自由」を謳歌できる時代がありましたが、現在では授業関連業務が細分化され、事務処理も増えています。大学・短大教員の働き方は、以前よりも「教育者」としての色合いを強める傾向にあります。
個人的な感覚としては、中学校や高校の教員とさほど変わりありません。部活がなくなって、代わりに研究活動が増えるイメージです。言い換えれば、勤務時間内に十分な研究時間を確保するのは至難の業です。
大学・短大教員の公務(事務・学生対応)

アドバイザー業務
多くの大学・短大では、教員がアドバイザーとして学生数十人を担当します。履修登録の相談、学業不振学生のフォロー、進級や卒業要件の確認など、責任は大きいものです。
正直なところ、時間割くらい自分で作って欲しいものですが、それすら出来ない学生が入学しているのも事実です。
また日本語が満足に出来ない留学生への対応もあります。留学にはN2相当の日本語力が必要とされますが、大学によってはそこまでの語学力がなくても入学させているケースが目立ちます。
このような学生は学業成績も振るわないことが多く、面談を実施する機会が増えます。
学生・保護者との面談
出席率や成績が著しく低い学生には、本人だけでなく保護者も交えて面談を行うケースがあります。短大では保護者との関係性が特に重要視される傾向があり、教員の対応力が問われます。
出席率や学業成績はアルバイトにのめり込むといった理由はもちろんのこと、基本的な生活リズムを自分で整えられないといった学生もいます。ここまで来ると小学校や中学校での指導事項ですが、大学教員が直面する現実です。
学生の時間割登録のサポート
一部の大学では「学生が自分で時間割を組む」という経験がまだ乏しいため、教員が履修相談を行う場面が多くあります。誤った履修登録によって卒業要件を満たせなくなる事態を防ぐためにも、教員の役割は不可欠です。
進路指導
卒業後の進路指導も大切な業務です。特に短大は就職率が重要な指標となるため、企業との連携や学生の就活支援に教員が積極的に関与する必要があります。
高校までと異なる点があるとすれば、事務職員やキャリアセンターがあり、基本的にはそちらで対応してくれることが多いです。
ですが、教員も企業研修に行く際に学生引率を行ったり、研修先企業への連絡を担うこともあります。もはや大学とはなにか自問自答する日々です。
大学・短大教員の研究活動

学会参加と研究紀要執筆
大学・短大教員は「教育者」であると同時に「研究者」でもあります。学会に参加し、研究紀要や論文を発表することは昇任や評価に直結します。
大学・短大は文部科学省が監督する機関による認証評価を受けます。認証評価では、短大であっても文部科学省からの指導により研究業績を求められる傾向が強まっています。
しかしながら短大・大学教員といえど研究力の高い教員ばかりではありません。信じられないことですが、教授クラスでありながら査読論文がほぼゼロというケースも見られます。
紀要は、もともとは学会の査読論文に落ちた論文を掲載するくらいの位置付けで、求めるような結果は出なかったものの、研究手法自体は確立されている必要があるものです。しかし現実には単なる授業レポートや小論文の域を出ない学術論文とは到底呼べないものが多く掲載されています。
それどころか数年に渡って論文を書かない教員すらいます。退官間近であればわからなくもないですが、年配の教員に限らないのが悲しい現実です。
研究費の現実
国公立大学に比べ、私立大学・短大では研究費の支給が少ないことが一般的です。年間15万円程度が上限というケースもあります。
学会参加の旅費は別に支給されるケースもありますが、学会費は研究費から捻出するケースが多いと思います。その上で、書籍・論文購入を考えると、決して十分とは言えません。文系であってもまともな論文を書こうとすれば自費での書籍購入は避けられません。
研究時間の確保の難しさ
授業・公務に追われる中で研究時間をどう確保するかは、教員にとって大きな課題です。「研究をしたいから大学に勤めた」という動機を持つ人にとって、現実とのギャップに悩むケースもあります。
しかしながら研究を行い論文を書かないと、よりまともな労働環境の大学への道がひらけないというジレンマがあります。
勤務時間と働きやすさ
労働裁量制ではなく時間管理型が主流
一般的に大学教員は裁量労働制というイメージがありますが、短大や私立大学では出退勤時間が明確に定められている場合も多く見られます。タイムカードで勤務を管理されるケースもあり、「研究に専念できる自由な時間」は意外と限られています。
部活動がないため定時帰宅も可能
高校の教員と異なり、短大教員には部活動指導の義務が基本的にありません。そのため、授業や公務が終われば定時で帰宅できる日も多いのが特徴です。ワークライフバランスを重視する人にとっては、大学教員の働き方は魅力的に映るかもしれません。
オープンキャンパス・入試日の勤務
ただし、大学運営に欠かせないオープンキャンパスや入試日の勤務は必須です。特に私大では学生募集に直結するため、夏休みや休日も出勤するケースがあります。
短大教員の将来性と課題
短大募集停止の現状
日本の短大は、少子化の影響を最も強く受けています。1993年には595校あったものの、2024年には297校にほぼ半減しています。さらに、2025年度に23校、2026年度に21校が募集停止します。
雇用の不安定さ
大学教員も任期制や契約制が増えており、短大教員はさらに厳しい状況にあります。専任教員のポストは限られ、非常勤講師として働く人も多いのが現状です。将来性を考えると、安定した雇用を求める人には厳しい環境かもしれません。
大学教員との違い
大学と短大を比較すると、短大教員は「教育者」としての役割が強く、研究に割ける時間や予算は限られています。一方、勤務時間は比較的規則的で、家庭との両立がしやすいという利点もあります。
今後のキャリア選択に向けて
大学・短大教員の働き方は「授業」「公務」「研究」を中心に、多岐にわたります。かつての自由度は薄れつつありますが、その分学生支援や社会的役割が拡大しているのが現状です。
特に短大教員は、教育面に大きな比重が置かれる一方、研究環境や将来性に課題を抱えています。少子化の進行によって短大の募集停止は増えており、今後も厳しい状況が続くでしょう。
それでも、学生一人ひとりと密接に関わり、教育を通じて社会に貢献できるという点では、大学・短大教員の働き方には大きな魅力があります。これから大学・短大教員を目指す方は、華やかなイメージだけでなく、現場の実態と将来性を理解したうえでキャリアを描くことが求められます。
高校や中学校教員から大学教員へのキャリアパスは別記事で解説しています。ぜひご覧ください。