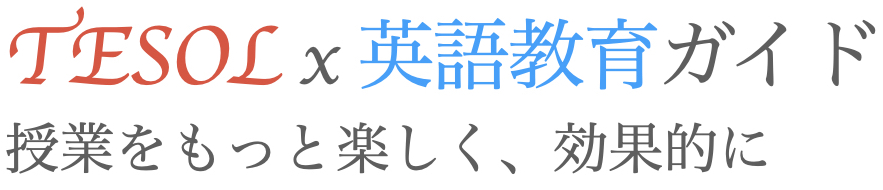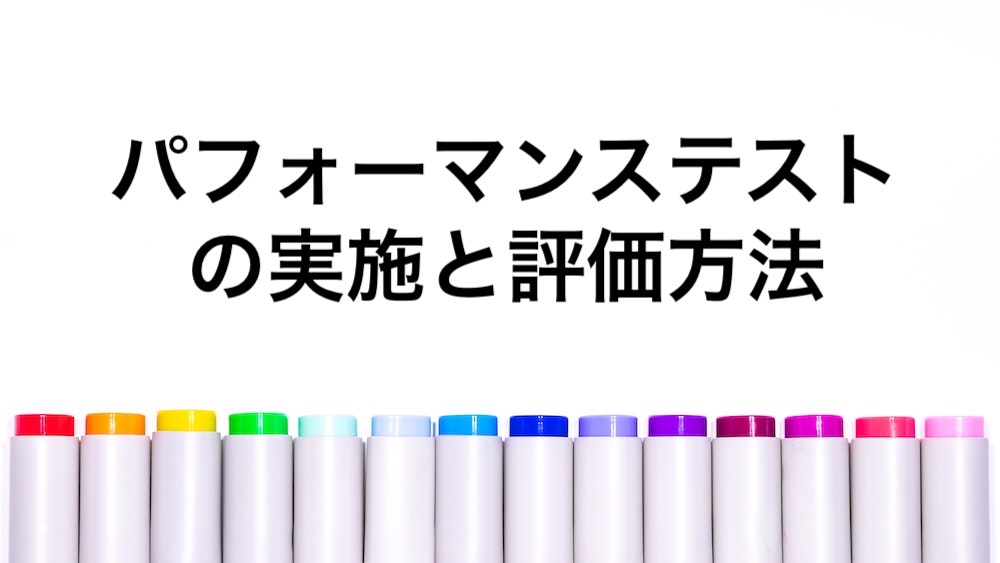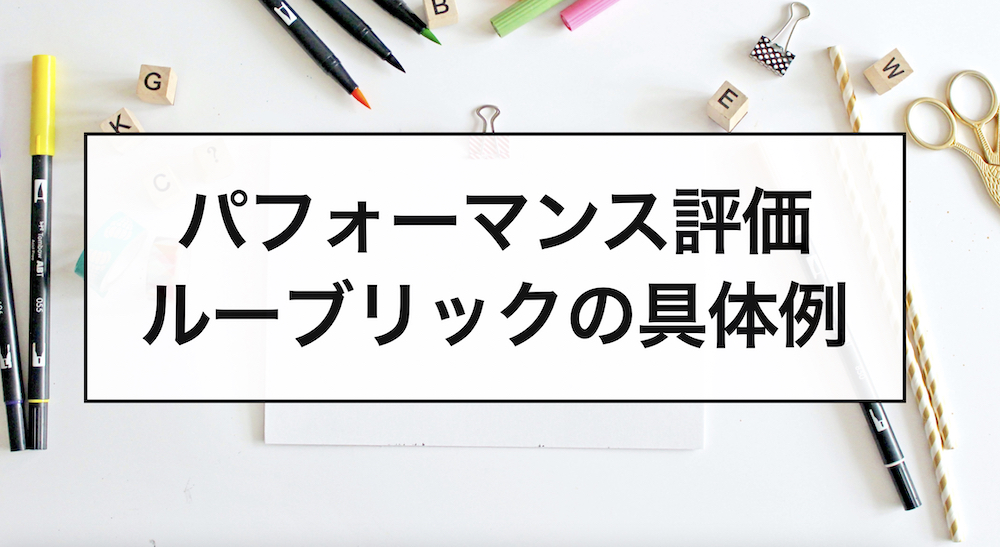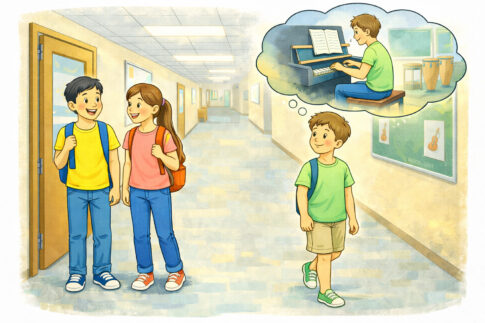実は英検1級・英国修士(TESOL/英語教授法)、現役英語教師のASAKOROKOです。
この記事では、英語を担当する先生が自校で自信を持ってパフォーマンステストを実施できるよう、基礎知識から実施のポイント、具体的な事例まで丁寧に解説していきます。
学校教育における扱いだけでなく、外国語教授法の分野における研究にも言及しながら、現実的な実施方法をルーブリックも含めてお伝えします。
なお、授業づくりの基本とChat GPT を使って授業準備や考査作成にかける時間を短縮する方法について知りたい方は、Udemyの講座がオススメです。
パフォーマンス評価とは

パフォーマンステストは、学習した内容を実際の場面で活用することができるかを評価するテストです。
評価に用いられる課題について、ウィギンズとマクタイは次のように述べています。
効果的に行動するために知識を活用する課題、あるいは、ある人の知識と熟達化を明らかにするような複雑な完成作品を実現する課題。(中略)多くの教育者は間違って、本当は「実技テスト」を意味しているときに、「パフォーマンス評価」という語句を用いている。
Wiggins & McTiche(著)西岡加名恵(訳)(2012:405)『理解をもたらすカリキュラム設計』
ウィギンズとマクタイも述べていますが、実技テスト=パフォーマンステストではありません。
わかりやすいように、スポーツ(サッカー)の例も交えて説明します。サッカーでは、ドリブルやシュートといった個々の技術があり、それらを活用してゲームや実践形式での練習が行われます。
実は英語の授業も同じで、文法や語彙といった知識、発音の技術があり、それらを活用してスピーキングやリスニング、リーディングやライティングが行われます。
サッカーでいうドリブルやシュートといった個々の技術、英語の文法や語彙の知識・発音の技術は、実技テストや伝統的なペーパーテストで評価可能です。一方で、試合中の動きやスピーキングなどの技能は実際にやらせてみないとわかないので、パフォーマンス課題で評価することになります。
まとめると、実技テストで求められるのは模倣で、伝統的なペーパーテストで求められるのは暗記と再生です。一方で、パフォーマンステストでは、判断力やクリエイティビティといった知識や技能を活用する力まで求められます。
外国語教育における似たような評価方法

外国語教育における似たような評価方法としては、TBLT(Task-Based Language Teaching)にもとづく評価があります。
TBLTにもとづく評価では、実際のコミュニケーションに類似したタスクへの取り組み状況を評価することになります。例えば、授業で道案内の方法を学習したら、実際に街へ出て道案内をさせるといったことも考えられます。
TBLTにおける評価方法は、実は2通りあります。1つ目が、タスク遂行度合いを評価する方法で、direct assessment of task outcomes と呼ばれます。極端な言い方をすれば、文法がめちゃくちゃで支離滅裂でもタスクが達成できればOKという考え方です。2つ目が、external ratings と言われる外部的な評価です。こちらは、文法の正確さなども評価対象となります。
いずれにしてもTBLTのフォーカスは、実際のコミュニケーションにおける言語使用にあります。タスク遂行を重視する場合はもちろん、文法の正確さなどを評価対象に加える場合でも、タスクをこなす中でどの程度扱えるかを重視しています。そういった意味で、TBLTにもとづく評価は先述したパフォーマンステストと同一の志向性を持つと考えられます。
では、学校の授業でTBLTにもとづく評価をそのままパフォーマンス評価として導入すればいいかと言うと、検討が必要な部分があります。導入の際に気をつけなければならない点について見ていきましょう。
学校でのパフォーマンス評価で気をつけること

TBLTのテストをそのまま学校でも実施できればという思いもありますが、現実的には、時間的な制約のほかに、次の3点について考えておく必要があります。
① 授業との関連性を保つ
学校でパフォーマンス評価を実施する場合、授業とのつながりは最重要視されるべき項目です。授業との関連性が薄くなると、児童生徒の授業へのやる気を低下させる原因となったり、不平不満の温床となります。
また、評価である以上、パフォーマンステストにも波及効果が伴います。児童生徒がパフォーマンステストに向けてどのような準備をすることになるのか、学習効果はどの程度あるのか見積もっておくことも必要です。
指導と評価を一体化させる重要性については、別の記事でも解説しています。
② 課題遂行に必要な知識・技能を指導する
テストには、熟達度テスト(Proficiency Test)と到達度テスト(Achievement Test)があります。熟達度テストとは、習った内容に関係なく、現在のレベルを測るテストです。TOEICや英検のようなテストをイメージすればわかりやすいと思います。一方、到達度テストとは、習った内容が定着しているかを測るテストです。
学校で扱うのは到達度テストです。パフォーマンス評価についても同様で、課題遂行に必要となる言語事項はすべて指導しておく必要があります。教師側で一度書き出し、すべて指導したか、達成の見込みがどの程度あるのかは見積もっておきましょう。
③ 信頼性・公平性を担保する
パフォーマンステストの結果を成績に含める場合は、信頼性と公平性を担保しなければなりません。この中でも特に危ういのが公平性です。評価する先生によって点数が大きく変わる事態などは避けなければなりません。
これまで見てきたように、学校でのパフォーマンステスト実施は、TBLTのテストをそのまま導入できるわけではなく、多くの制約を受けることがわかります。担当する学校や学年によっても制約は異なると思いますが、ここでは、パフォーマンステストの事例として4つ紹介していきます。
※教員間での採点のばらつきや問題の流出など、公平性に関する問題については、記事の最後にQ&Aとしても触れています。
事例1. 【小中高】インタビューテスト

生徒に英文を読ませて教師が質問する方式で、英検の2次試験と同様の流れです。
読ませる英文を教科書本文にすることで、授業との一体化もさせやすく、どのレベルでも実施できるのもポイントです。
- 入室
- 本文の音読
- 本文に関する質問
- 自分自身に関する質問
- 退出
具体例
T: Let’s begin the test. Here’s a card for you. Please read it aloud.
それはテストを始めましょう。カードです。音読してください。
S: (生徒音読)
T: Now, let me ask you a question.
では、質問します。(内容理解の質問)
S: (生徒回答)
T: OK. Please return the card. I will ask you another question.
はい、ではカードを回収します。別の質問をします。(カード回収・生徒自身に関する質問)
S: (生徒回答)
T: OK. This is the end of the test. You may go now.
はい、これでテスト終了です。退出してください。
評価のルーブリック
| 項目/評価 | A | B | C |
| 音読 | 間違いなく読める | 読み方に間違いがある | 最後まで読めない |
| 内容理解 | 正確に答えられる | 文法的な誤りがある | 答えが間違っている |
| 自己表現 | 正確に答えられる | 文法的な誤りがある | 発話の趣旨が理解できない |
実施・評価のポイント
ルーブリックはできるだけ簡潔にわかりやすくした方が、評価者によるブレが少なくなります。また、今回の例では、質問を1回ずつしかしていませんが、質問の個数を増やすことでより信頼できるテストになります。
このように実施しやすく、信頼性も高められるインタビューテストですが、デメリットもあります。インタビューテストでは、タスクや場面に対応する能力を測定できません。実践的なコミュニケーション力を評価するには、次に紹介するロールプレイが必要です。
【インタビューテストのまとめ】
| 対象 | 小学校・中学校・高校 |
| 実施時間 | 1人あたり3〜5分 |
| 区分 | やり取り |
| 英検レベル | 5級〜 |
事例2. 【小中】シチュエーション・ロールプレイ

場面に応じたコミュニケーション能力を評価するには、シチュエーション・ロールプレイがオススメです。場面の書かれたカードを生徒に渡し、その場で対応してもらう形式のテストです。
シチュエーション・ロールプレイは、工夫次第では高校でもできますが、場面と言語事項のつながりが強い小学校・中学校での授業に特にオススメの方法です。
小学校での実施例
場面カード
クラスに新しいALTの先生が来ました。先生がALT役を演じますので、英語で自己紹介してください。
具体例
S: My name is Hinano Koyama. Nice to meet you.
コヤマ・ヒナノです。よろしくお願いします。
T: Nice to meet you, too. What can I call you?
こちらこそよろしくお願いします。なんて呼んだらいいですか?
S: Just call me Hina.
ヒナで構いません。
T: What is your hobby, Hina?
ヒナの趣味はなんですか?
S: Soccer. I belong to a soccer club.
サッカーです。サッカークラブに入っています。
評価のルーブリック
| 項目/評価 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 挨拶 | フルセンテンスで伝えることができた | 単語を並べて伝えることができた | 伝えることができなかった |
| 呼び方 | |||
| 趣味 |
小学校でのポイント
小学校でロールプレイを実施する場合は、場面設定が大きなポイントになります。使う表現は、設定する場面によって決まります。ロールプレイ遂行に必要となる言語事項をあらかじめ確認し、指導しておきます。ロールプレイでは、それらを実践に近い形式で使うことができるかどうかを評価していきましょう。
もっと詳しく知りたい方には、小学校英語サポートBOOKS – 単元末テスト・パフォーマンステストの実例つき! 小学校外国語活動&外国語の新学習評価ハンドブック もオススメです。
中学校での実施例
場面カード
留学生に町を案内することになりました。スケジュールは次の通りです。留学生に予定を伝えてください。先生が留学生役になります。
10:00 – 12:00 City History Museum
12:00 – 13:00 Lunch (Japanese restaurant)
13:00 – 15:00 Free time
具体例
T: I heard that you will be my city-tour guide. Thank you. So, where will we go?
町を案内してもらえると聞きました。ありがとう。それで、どこへ行きますか?
S:(生徒返答)
T: Oh, that sounds interesting. Where will we go in the afternoon? Any recommendation?
それは面白そうですね。午後はどこへ行きますか。どこかオススメはありますか?
S:(生徒返答)
T: What is the reason you recommend it?
オススメする理由はなんですか?
S:(生徒返答)
評価のルーブリック
| 項目/評価 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 午前の予定 | 8割以上を文法的に正しい英文で伝えることができた | 5割以上は文法的に正しい英文で伝えることができた | A・Bに該当しない |
| 昼食 | |||
| 午後の予定(文法) | |||
| 午後の予定(内容) | 理由をつけて提案することができた | 予定を提案することができた |
中学校でのポイント
中学校では指導する文法と場面を結びつけるのがポイントです。習った文法事項を実際のコミュニケーションに近い場面で活用することができるか評価していきましょう。
書籍では、文法指導とパフォーマンステストのつながりを学年別にまとめているこちらのシリーズがオススメです。
【シチュエーション・ロールプレイのまとめ】
| 対象 | 小学校・中学校 |
| 実施時間 | 1人あたり3〜5分 |
| 区分 | やり取り |
| 英検レベル | 5級〜3級 |
事例3. 【中学校】リポート・スピーチ

会話文が書かれたカードを渡し、要約させます。教科書本文がダイアローグで構成されている場合に効果的なテストです。
① 生徒入室・カードを渡す
② カードの音読 or 黙読
③ 会話の要約
④ カード返却・退室
具体例
T: Here’s a card for you. Please read it silently for 20 seconds.
カードです。20秒黙読してください。
T: What are people talking about in the dialogue?
ダイアローグでは、人々は何について話していますか?
S: They are talking about an electric car.
彼らは電気自動車について話しています。
T: What did John and Dan say?
ジョンとダンは何と言っていますか?
John said it was cool and many people would buy it, but Dan said it was too expensive.
ジョンはカッコイイ、多くの人が買うだろうと、しかし、ダンは高価すぎると言っています。
評価のルーブリック
| 項目/評価 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 話題 | 文法的に正しい英文で伝えることができた | 文法的な誤りはあったが、内容を伝えることはできた | 単語の羅列になってしまったか、伝えることができなかった。 |
| Johnの発言 | |||
| Danの発言 |
実施のポイント
会話文のリポートでは、tell や say, ask といった動詞の使い方について指導しておくようにしましょう。時制の一致と人称の変更に注意が必要です。
他人から聞いたことを伝える場面は意外と多いので、実生活でも役立つスキルです。最初に紹介したインタビューと組み合わせて実施するのもオススメです。
【リポート・スピーチのまとめ】
| 対象 | 中学校 |
| 実施時間 | 1人あたり3〜5分 |
| 区分 | やり取り |
| 英検レベル | 3級 |
事例4. 【高校】リテリング

リテリングは、読んだり聞いたりした話を自分の言葉で伝える再話活動です。パフォーマンステストとして使う場合は、教科書本文を使うことで授業との関連性を持たせやすくなります。
①入室・カードを渡す
②カードの音読
③リテリング
④カード返却・退室
| 項目/評価 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 音読 | 間違いなく読めた | 読み方に間違いがあった | 最後まで読めなかった |
| 文法 | 8割以上を文法的に正しい英文で伝えることができた | 5割以上は文法的に正しい英文で伝えることができた | A・Bに該当しない |
| 内容 | 概要・詳細ともに伝えることができた | 概要を伝えることができた | A・Bに該当しない |
| 流暢さ | 言い淀みなく伝えることができた | ところどころ言い淀みがあった | 言い淀みが多かった |
リテリングについては、こちらの記事で指導法についても詳しく扱っています。
書籍では、 佐々木啓成先生の『リテリングを活用した英語指導—理解した内容を自分の言葉で発信する』 が詳しくオススメです。
第2章 リテリングの手順(Ⅰ):内容理解
第3章 リテリングの手順(Ⅱ):音読による内在化
第4章 リテリングの手順(Ⅲ):発話情報の選定
第5章 リテリングの手順(Ⅳ):英語への変換
第6章 リテリングの手順(Ⅴ):発話
第7章 どのようにリテリングを評価するのか
第8章 リテリング研究から分かること
リテリング以外では、短時間で効果抜群! 英語4技能統合型の指導&評価ガイドブック (目指せ! 英語授業の達人) がオススメです。指導と評価がセットで紹介されています。
新学習指導要領の観点別評価にもとづいたテストであれば、こちらの書籍がおすすめです。
【リテリングのまとめ】
| 対象 | 高校 |
| 実施時間 | 1人あたり3〜5分 |
| 区分 | やり取り・発表 |
| 英検レベル | 準2級〜 |
パフォーマンステスト実施のQ&A

先生によって評価にバラつきが生じてしまう
バラつきが出るのは仕方ないので、バラつきが出るのを前提に、計画していきましょう
正直に言って、バラつきをなくすのは困難を極めます。ある先生が、別の先生より甘くつける傾向があったり、厳しくつけすぎる傾向があるのは、どうしても避けられません。
ここで問題になるのは、評価の公平性です。児童生徒からすれば、評価の甘い先生にテストしてもらいたいというのが当然です。
そこで、学期や年間を通して、すべての先生に同じ回数だけ評価してもらえるよう計画します。
例えば、中間テストでA先生にテストしてもらった生徒は、期末ではB先生に。中間でB先生だった生徒は、期末ではA先生に、というように回数を合わせておきます。
オススメしないのは、得点の調整です。ある先生に出来る生徒がたまたま偏っていたり、できない生徒ばかりだったということはあり得るので。
また、評価が真逆になってしまうのは問題です。ある先生が10点をつけた生徒に対して、別の先生が3点しかつけないというのは、おかしい可能性が高いので、評価基準について話し合いましょう。
テストの順番について不平不満が出てしまう
年間を通して公平になるように調整をしましょう
パフォーマンステストでは、前の児童生徒がテストしている間、ほかの児童生徒には待ち時間が生じますが、準備が十分でないからテストをあとに受けたい、休み時間に短期記憶に突っ込んだから逆に早く受けたいという生徒は必ず存在します。
そこで、学期や年間を通して待ち時間が公平になるように調整します。
中間テストでは出席番号順に、期末テストでは逆順に、となるように工夫するだけで、テストを受ける前の待ち時間は均等になります。
テスト問題が児童生徒の間で出回ってしまう
一斉実施 or 流出前提の出題設計で乗り切ります
あるクラスがほかのクラスより先にテストを実施し、問題が他クラスに流出するのはよくあることです。小規模校であれば、すべてのクラスを一斉に実施することも可能かもしれません。
一斉実施が難しい場合は、流出しても意味がない出題設計にしておきます。
例えば、教科書のレッスンのうち1についてリテリングしてもらう、授業プリントに掲載されているQ&Aから出題する、授業中に扱ったディスカッションのトピックから出題する、といったように公表してしまいます。
授業との関連性も強くなるので、指導と評価が一致しますし、児童生徒もパフォーマンステストに向けて練習するようになるので、出題内容の公表はかなりオススメです。
パフォーマンステストの時間が確保できない
評価者を増やすしかない
パフォーマンステストは、短いものでも1人あたり2〜3分はかかってしまいます。40人クラスであれば、2時間かかってしまいます。
テスト時間をこれ以上短縮するのは現実的ではないので、評価者を増やすことになります。2人で20人ずつ評価すれば1時間程度に短縮できます。
先生によって評価にバラつきが生じる可能性はありますが、学期や年間を通して均一になるように計画しておけば大丈夫です。
パフォーマンステストに向けて指導する

記事の前半でもお伝えしたように、指導と評価の一体化は重要です。乖離すると不平不満の温床となります。
パフォーマンス評価を計画したら、課題遂行になる英単語や英文法はもちろんですが、スピーキングの練習も増やしていくのがオススメです。
やり取りの指導の方法には、スモールトークなどを上手に活用していきましょう。スピーキングの活動例は別の記事で紹介しています。
パフォーマンステストについて、さらに学ぶには
パフォーマンステストは、新学習指導要領にもとづいた授業を評価と一致させるうえで、欠かせない評価方法です。
ですが、自分ですべて用意しようとするとテストのアイディアを出すのも大変ですし、準備に時間がかかりすぎてしまうので、講座や書籍を参考にするのがオススメです。
【Udemy授業づくり講座】
【小学校】
【中学校】
【高校】