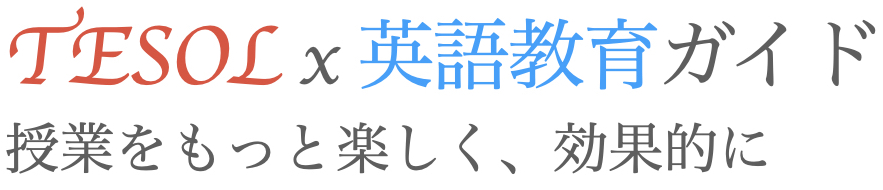実は英検1級・英国修士(TESOL/英語教授法)のASAKOROKOです。
授業は経験を積めば上達すると思われていますが、必ずしもそうではありません。
あまり大きな声では言えませんが、ベテランでも満足に授業ができない教員も見てきましたし、若くても上手く指導している先生もいます。
授業は、単に回数をこなせば上達するのではなく、授業力を高める取り組みが必要です。
逆に言えば、しっかりと取り組めば経験の浅い先生でも、良い授業を継続的に実施することが可能になります。
そこで、この記事では、次の2点について重点的に扱っていきます
- 授業力とは、なにか
- 授業力を高めるには、どうしたらいいか
授業準備や考査作成は、Chat GPT を活用すればあっという間に仕上げることも可能です。Chat GPT など 生成AI の活用は、Udemy の講座で解説しています。
1. 授業力とは
授業力に学術的な定義はありませんが、次のように考えられます
授業力とは「授業をするのに必要になる力」で、次の4つの能力・知識が含まれます。
◉ 授業を準備・実施・評価・改善する力
◉ 教科の専門知識
◉ 教育方法の知識
◉ 児童生徒を理解する力
授業をするには、前段階として準備があり、実施後は、評価し、改善へと繋げていくことになります。
これらは誰にでも出来るかというと、そうではなく、指導する教科の専門知識、指導方法の知識が必要です。
また、授業は児童生徒に合わせて行うものなので、児童生徒を理解する力も必要です。
このように考えてみると、次のように整理できます。
◉ 授業に直接的に関わっているのは、授業を準備・実施・評価・改善する力
◉ 教科や教育方法の専門知識・児童生徒理解は、間接的にこれらを支えている
イラストにすると、次のようになります。

この記事では、授業に直接関わる準備・実施・評価・改善する力を伸ばす方法について、まとめていきます。
2. 授業を準備する力を高める
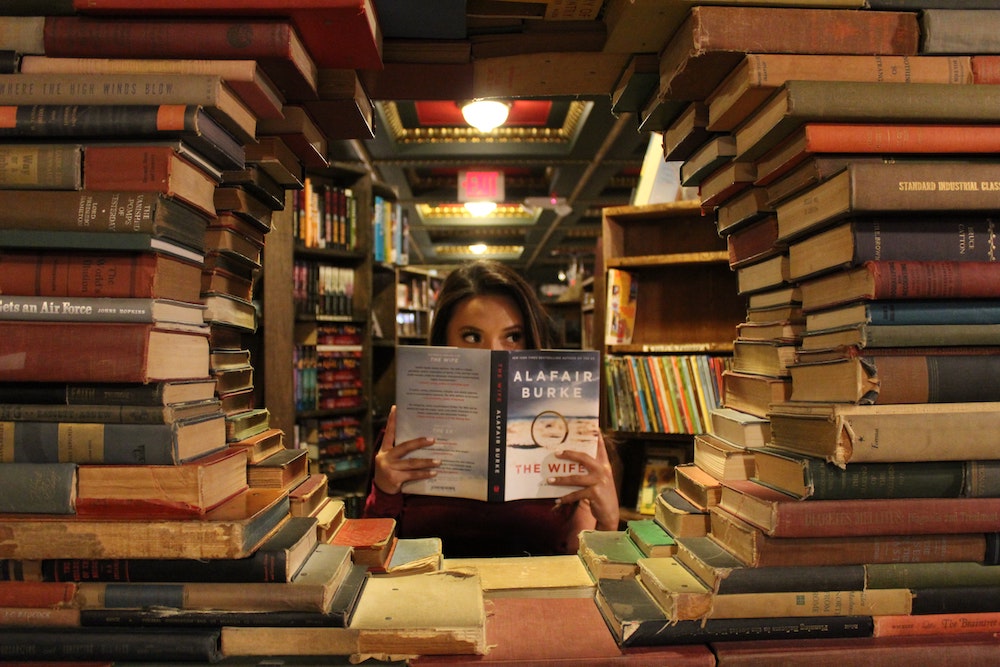
授業を準備する力には、次の2つがあります。
⑴ 指導計画を立てる力
⑵ 教材研究・作成力
⑴ 指導計画を立てる力
指導計画を立てる際のポイント、実は「順番」です
次の順に考えていきましょう。
◉ 年間指導計画→単元の計画→本時の計画
◉ 指導目標→評価→学習活動
このように計画することで、年間を通して一貫した指導が実現できます。
1時間の授業では大きな成果は望めませんが、単元や年間を通じて一貫して指導すれば、それも可能になります。
また、学習活動より評価を先に決めることで、指導目標を具体化するとともに、学習活動との乖離を防ぎます。
⑵ 教材研究・作成力
教材には、児童生徒と指導内容をつなぐ重要な役割があります
教材(教科書)は、次の観点から授業前に検討されるべきです。
◉ 教材が、児童生徒とマッチしているか
◉ 教材が、指導理論を反映しているか
児童生徒にとって難しすぎたり、易しすぎてもいけませんし、ニーズがズレているのも困りものです。
また、教科書は必ずしも、最新の指導理論を十分に反映しているとは言えません。
教師側で教材を新たに作成したり、補うことも必要になります。
3. 授業を実施する力を高める

⑴ 指導技術
指導技術は、学習活動を進める上で必要になる力です
指導技術には、次のようなものが含まれます。
- わかりやすく説明する
- 的確に指示を出す
- 発問する
- 間を取る
- 板書する
- 指名する
- 机間指導
説明の仕方などは、予備校講師の授業も参考になります。
⑵ 軌道修正する力
授業中に軌道修正ができるようになるには、次の2つが必要です
◉ 児童生徒の理解度を見取る力
◉ 状況に合わせて、プランBを立てる力
児童生徒の理解度は、下位層・中間層・上位層に分けて考えると、わかりやすいです。
中間層が理解していない場合は全体指導が必要ですし、下位・上位の児童生徒には個別対応も考えられます。
プランBは、その場で適切に立案するのは至難の業です。
少なくとも次のような事態は事前に想定し、対策を考えておきましょう。
- 児童生徒が、思ったより理解できなかった/簡単に理解できてしまった
- 思ったより活動に、時間がかかった/かからなかった
- 一部の児童生徒のみが、できなかった/すぐできてしまった
⑶ 授業規律を保つ力
授業規律は、次の手順で進めると安定します。
1. 規律を設けることに納得させる
2. 授業中のルールを決める
3. ルールを浸透させる
4. 規律を顕在化させる
5. 規律を守れない児童生徒に対処する
4. 評価・改善する力を高める

評価・改善には、次の2種類があります。
- 児童生徒の学習評価・改善
- 授業自体の評価・授業改善
⑴ 児童生徒の学習評価・改善
形成的に評価し、フィードバックしていきます
学習の進捗度合いを形成的に評価するには、次のような方法があります。
- 観察
- 小テスト
- 問題演習
- ノート・ワーク
- レポート
授業中は観察に頼ることが多くなりますが、注意が必要です。
どうしても見落としはあるものですし、観察時にたまたま出来ていた・出来ていなかったということもあります。
多角的に分析するよう努めると、児童生徒の理解度も上がります。
形成的な評価は、授業の終わりに、まとめとして児童生徒に伝えることをオススメします。
何が出来るようになって、何に課題があるのかをフィードバックすることで、家庭学習の指導へと繋げていきます。
⑵ 授業自体の評価・授業改善
授業改善の基本は、PDCAのサイクルです。

PDCAを回すためには、指導と評価を一体化させる必要があります。
授業と評価がズレていると、児童生徒も不満を持ちますが、教師も授業改善に必要な情報が手に入りません。
授業づくりについて学ぶには
授業づくりは、Chat GPT を上手に活用することで、時間を短縮して質の高い指導計画を立てることができます。
Chat GPT の活用術は Udemy の講座で解説しています。講座では、日本や欧州における生成AIの教育利用についても解説しています。生成AIに対する不安感もしっかり解消します。