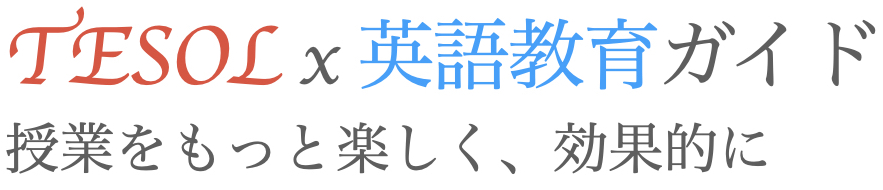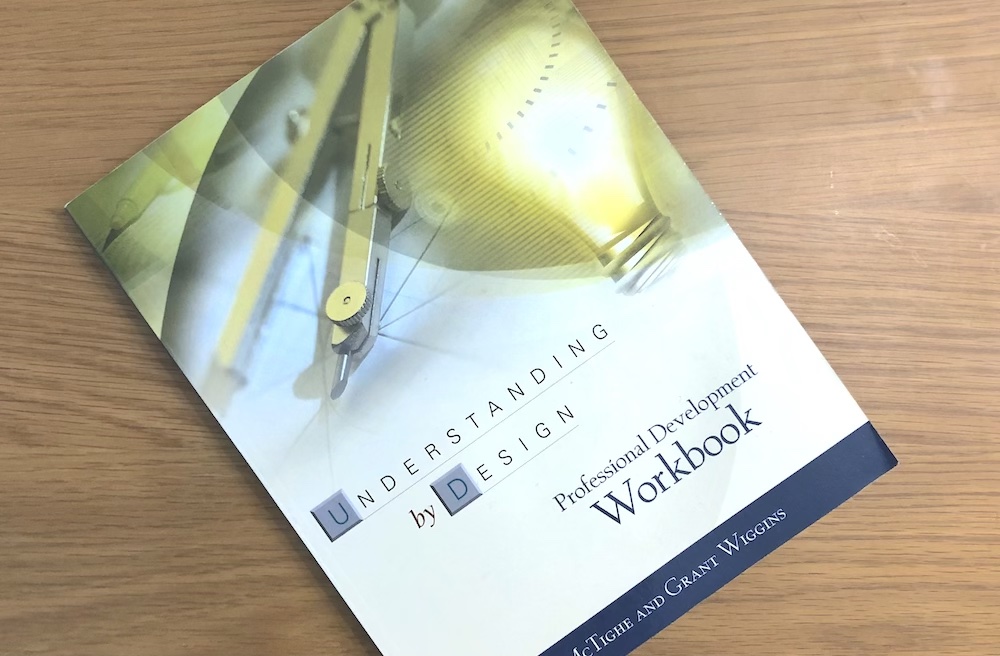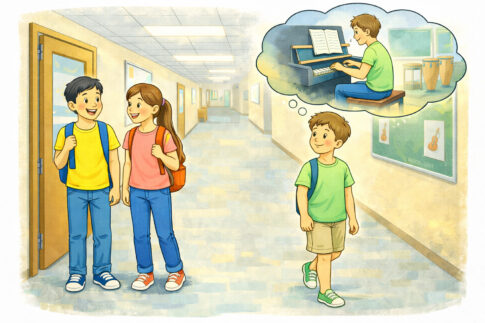英検1級・英国修士(TESOL/英語教授法)、英語教師のASAKOROKOです。今回は、CAN-DOリストとはなにか? 作り方と上手な活用法について、簡単にわかりやすく解説していきます。
- CAN-DOリストとは?(メリット・デメリット)
- CAN-DOリストの作り方と使い方
- CAN-DOリストの事例(小学校・中高・小中高連携版)
なお、CAN-DOリストだけでなく、指導と評価を一体化した授業づくりをしたい方には、Udemy の講座もおすすめです。Chat GPTで授業準備と考査作成にかける時間を劇的に短縮する方法についても解説しています。
CAN-DOリストとは?

CAN-DOリストとは?
CAN-DOリストは、児童生徒が英語でできることをリスト化したものです。
コミュニケーション行為をベースに「~できる」という形で表記されます。
CAN-DOリスト作成のメリット
CAN-DOリストには、次のようなメリットがあります。
- 生徒が身につけるべき能力が、4技能5領域ごとに明確化でき、指導と評価の改善に活用できる
- 「なにができるようになるか」が明確で、言語活動やパフォーマンス・テストと結びつけやすい
- 自己評価が容易で、主体的に学習に取り組む態度の育成に活用できる
- 小中高での連携が図りやすくなる
CAN-DOリストを用いることで、指導と評価、教材が一体化し、よりコミュニカティブな授業へとつながります。
児童生徒にとってもわかりやすく自己評価につなげやすいですし、小中高での連携もしやすくなります。
CAN-DOリストに対する批判(デメリット)
良いことばかりに聞こえるCAN-DOリストですが、次のような批判もあります。
教科書が変わらないと意味がない
自校の児童生徒の実態に合わせてCAN-DOを作成し、指導計画を立てると、教科書をはじめとする教材との不一致が明確になります。
指導したいことが教科書に掲載されていない、教科書の活動が難しすぎる、簡単すぎる、など、様々な問題に直面します。
結局のところ、教材がなければ指導はできません。CAN-DOリストを活用するには、教科書以外にも教材を作成して、上手に授業を組み立てていく必要があります。
教材作成の手間はありますが、CAN-DOリストにはメリットも多いです。前向きな気持ちで作ってみるのも◎
CAN-DOリストの作り方と使い方

CAN-DOリストの作り方と使い方は、文部科学省の資料によれば、以下の6ステップです。
CAN-DOリストの目的を管理職や英語担当教諭で共有する
卒業時の学習到達目標を設定する
生徒の学習の状況等を踏まえた上で、卒業時の学習到達目標を「~することができる」という形で、4技能5領域ごとに記述します。
学年ごとの学習到達目標を設定→単元計画の作成
卒業時の学習到達目標から、学年ごとの目標を「~することができる」という形で、4技能5領域ごとに設定します。
その上で、各単元における目標を「~することができる」という形で記述し、主な学習活動、評価方法を計画します。
授業の実施と評価
多肢選択形式等の筆記テストのみならず,面接,エッセー,スピーチ等のパフォーマンス評価を活用していきましょう。
達成状況の把握
各単元の目標や学年ごとの学習到達目標の達成状況を把握し,指導や評価 の改善に生かす。必要に応じて教科書の採択に生かす。
学習到達目標の見直し
設定した卒業時及び学年ごとの学習到達目標が適切であったかどうかを検討し,必要に応じて見直す。
文部科学省
「各中・高等学校の外国語教育における 「CAN-DO リスト」の形での 学習到達目標設定のための手引き」
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1332306_4.pdf
CAN-DOリストを使って、児童生徒に自己評価させるのもオススメです。主体的に学習に取り組む態度の育成につながりますよ。
CAN-DOの書き方
CAN-DOは「~することができる」という形で書くのですが、ポイントが3つあります。
- 「どのようなタスクができるか」を書く
- 「どのような言語の質でできるか」を追記する
- 「どのような条件下でできるか」を追記する
STEP1 「どのようなタスクができるか」を書く
タスクとは、言語活動のことです。ここでは、自己紹介を例に解説していきます。
聞くこと
自己紹介を聞いて、氏名や趣味、好きなことなどを聞き取ることができる
話すこと(やりとり)
自分の氏名や趣味、好きなことを自己紹介で伝えることができる
STEP2 「どのような言語の質でできるか」を追記する
言語の質というのは、レベルのことです。どのようなレベルで達成させたいのか、到達基準を示します。今回は「簡単な語句や基本的な表現」という文言で、難易度を下げてみます。
聞くこと
自己紹介を聞いて、氏名や趣味、好きなことなどの簡単な語句や基本的な表現を聞き取ることができる
話すこと(やりとり)
自分の氏名や趣味、好きなことを簡単な語句や基本的な表現を用いて自己紹介で伝えることができる
STEP3 「どのような条件下でできるか」を追記する
必要であれば「どのような条件下でできるか」追記します。今回は「ゆっくり話してもらえば」「限られた範囲であれば」というように条件をつけ、言語活動の難易度をさらに下げてみます。
聞くこと
ゆっくり話してもらえば、自己紹介を聞いて、氏名や趣味、好きなことなどの簡単な語句や基本的な表現を聞き取ることができる
話すこと(やりとり)
自分の氏名や趣味、好きなことなど限られた範囲であれば、簡単な語句や基本的な表現を用いて自己紹介で伝えることができる
パフォーマンス課題と結びつける
CAN-DOリストと言語活動だけでは不十分ですよね。パフォーマンス課題を設定し、指導と評価の一体化を図りましょう。指導と評価の一体化の重要性については、別の記事で解説しています。
パフォーマンス課題の例は、こちらの記事をご覧ください。ルーブリックの作成と合わせて解説しています。
CAN-DOリストが活用できない!?

CAN-DOリストが活用できない、活用しづらいと感じている方は、次の2点を確認してみてください。
- CAN-DOリストと言語活動が結びついているか
- CAN-DOリストと教材が一致しているか
①CAN-DOリストと言語活動の結びつき
このようなCAN-DOリスト作っていませんか?
日常的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、簡単な語句や文を用いて伝えたり、相手からの質問に答えたりすることができる。
(札幌市CAN-DOスタンダード, 中学校 やりとり)
とても良いCAN-DOだとは思います。年間計画などでよく見かけますよね。
ですが、これを見て、授業で行う言語活動が思い浮かびますか? 表現が抽象的で、イメージしづらいです。
そこで、単元やレッスンごとに、より具体的なCAN-DOを設定していきます。例えば、この場合は、次のような具体的なCAN-DOが考えられます。
- 週末の出来事と感想をペアで共有し、相手に質問したり、質問に答えることができる
- 好きな教科の学習内容と感想をペアで共有し、相手に質問したり、質問に答えることができる
- 学校行事に向けた取り組みと感想をペアで共有し、相手に質問したり、質問に答えることができる
ここまで具体化できれば、授業中の活動を計画できそうですよね。帯活動でペアワークさせてみようかな、とか、どんなプリント用意しようかな、とか、考えられるようになります。
②CAN-DOリストと教材の一致
CAN-DOリストを具体化すると、CAN-DOと教材が一致していないことに気づくことが多いです。
例えば、次のようなCAN-DOを単元目標として設定し、帯活動で取り組むことにしたとします。
好きな教科の学習内容と感想をペアで共有し、相手に質問したり、質問に答えることができる
このCAN-DOは、さらに以下のCAN-DOに分解できます。
- 教科名が英語で言える
- 教科の学習内容が英語で言える
- 自分の気持ちを表す表現が言える
- 疑問文が作れ、受け答えができる
自分の気持ちを表す表現や疑問文は、教科書でも取り扱いがあるはずです。各教科の英語名も巻末などにまとめて記載されているかもしれません。
教科の学習内容までは記載されていないことが多いです。辞書指導で対応するのか、ハンドアウトを作成するのか、何かしらの工夫が求められます。
CAN-DOリストの事例

小学校 CAN-DOリストの事例
中学校・高校版
【高校】令和4年度 CAN-DO形式での学習到達目標リスト【公立高等学校】 (秋田県)
小中高連携版
札幌市CAN-DOスタンダード(札幌市モデル「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標)小・中・高つながり編
CAN-DOリストが学べる本
小学校編『小学校英語「5領域」評価事例集』
Can do リストは、パフォーマンス課題と結びつけることで、使いやすさが格段にUPします。パフォーマンス課題との繋がりを意識するのがオススメです。
本書は、Can do リストだけを扱ったものではありませんが、Can do リストの作成と活用についても触れらています。評価との結びつきを意識できるので、Can do リストだけを扱った専門書より実践的でイチオシです。
中学校編『新学習指導要領が実践できる! 中学校英語授業パーフェクトガイド』
CAN-DOリストは、しっかりと活用すれば、強力なツールとなります。新学習指導要領とも非常に相性が良いです。
本書では、新学習指導要領にも対応してCAN-DOの作成・活用が解説されています。文部科学省教科調査官も務めた向後秀明氏による著書です。
高校・専門書編『教材・テスト作成のためのCEFR-Jリソースブック』
高校の先生やCAN-DOリストを専門に学びたい方にオススメの1冊です。CEFRを文法や4技能の指導にどのように生かしていくか議論されています。CAN-DOリストの作成や見直しにも◎
CEFR-Jに即した文法・語彙、テスト作成とは?
日本人学習者の英語力の伸長を表す汎用参照枠・CEFR-J。そのCAN-DOリスト構築法を紹介した『CEFR-Jガイドブック』に続き、CEFR-J各レベルに対応した文法・語彙がどのようなものか、またレベルに応じたタスクやテストはどのように作成したらよいか、最新のプロファイリング研究に基づく CEFR-J活用「リソース」を掲載した第2弾。
コミュニケーション中心の授業づくりに向けて
CAN-DOリストはあくまでも計画です。CAN-DOリストを上手に活用していくには、教材作成や指導技術も必要です。
イチオシはUdemyの授業づくり講座です。すぐに使える指導技術を学ぶことができます。Chat GPTで授業準備や考査作成にかける時間を短縮する方法についても学ぶことができます。
学習者中心のコミュニカティブな授業づくりを学ぶには、CELTAがオススメです。ケンブリッジ大学英語検定機構認定で、国際的評価も非常に高いです。2020年からはオンラインでも受講可能になりました。
CELTAは費用やスケジュールの面でハードルが高いという方には、Diploma in TESOL もオススメです。こちらは自分のペースで学習でき、230~300ドル前後で取得できます。検討してみるのも◎